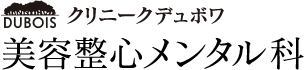老年期
老年期とは何か
老年期と言う人生のあるステージ、期間はいつごろを指すかと言うと、有名なエリクソンの8段階ライフサイクル斬成論では55歳以上になっているが、壮年期と老年期の間に過渡的な期間を設けるべきとする考えがあり、55歳から65歳を向老期とする考え(神谷美恵子)や、同じように「初老期」「中老期」という言い方もある。
最近、日本老年学会が従来の65歳以上を高齢者とする考え方を改めるよう提言した。65から74歳を准高齢期、75~89歳以上を高齢期、90歳以上を超高齢期とする案である。
エリクソンも晩年には、80代後半以降は老年期から外して9番目の段階にすべきであると述べている。
それらを勘案して、私は55歳~64歳を思秋期、65歳から74歳を前老年期。75歳~89歳を老年期、90歳以上を晩年期(晩期老年期)とするのが妥当ではないかと考えている。
思秋期とした理由は「思秋期」のところで述べている。
成人・壮年期に、心身の若さが下降局面に入ったとハタと思う瞬間があり、その時に人は老いの予期不安を覚えるが、思秋期に入ると老いることが確信に変わり、老年期には現実のものになる。
人は選択的無自覚にとでもいうかのように「老・死」を自分とは無関係なものと否認しつつ生きているものであるから、老化の自覚は不意に突如として現れ、ショックとして体験される。
生物学的老化について
ところで老化とは何をいうのだろうか。
生物学的に見ると、多細胞生物である人間は、体細胞の分裂回数が有限である、つまり体細胞には寿命があることから、個体の死は必然のものであり、同時にそれは老化を伴うことを意味する。細菌など単細胞生物では2分裂をして命をつないでいくので、死というものがないから老化もないのである。
人間と言う個体はそもそも有限の時間を生き、個体が衰え死んで行くということは、生物の目から見れば、生の場を次の世代に譲り渡すという意味でしかない。
生物学的に見れば、生きることの本質は、個体が生きながらえることではなく、生命が連続して行くことである。つまり、子孫を残すものを生物、すなわち生命のあるものと定義しているとも言える。その方法として、多細胞生物(動物、人間)は有性生殖を選んだために、個体の死、個体の老化と言う問題が生じたのである。
人間という生物はそもそも有限の時間を生きるという選択をした生物の仲間であるということを念頭において老化という問題を考える必要がある。
人間も老化に伴って必然的にエントロピーは増大し、それは生理的機能を減退させ、それを生理的老化と言う。
老化とは、「加齢にともなう生理的機能の減退」と定義されるが、生理的には「加齢に伴う緩やかな全身の臓器の機能の低下とホメオスターシス機能の低下である。」と言える。
しかし人間においては、老化は一律的には訪れず、多様性に富み個体差が非常に大きいのが特徴である。
発生においては、たった一個の細胞である受精卵が卵割を始め細胞の機能が分化して行く過程は殆ど個体差が無い。まさに神秘的に、正確な遺伝子のプログラムに従って進行する。つまり人の妊娠から出産の過程では、それほど大きな個体差はない。それに比べると老化は、それがいつ始まるのか、何が起きると老化というのかさえはっきりしない。また個体差は甚だしく、人間の場合65歳以上を老人と呼ぶと言っても、その時点での様子は、人によって非常に違ってくる。どう見ても発生のように、念を入れたプログラムが作られているようには見えない。かといって老化しない個体はないのだから何かのプラグラムは存在しているに相違はない。いずれにしても老化のプログラムは発生に比べると著しく迫力に欠けるのである。
また免疫学者の多田富雄によれば、老いは極めて非生物学的現象であって、「発生」や「分化」と言う均衡の取れた生物学的現象に比べるとそれは余りに不整合で、不自然な現象であるという。
人は皆絶え間ない新しい老いの段階に直面していく。老いには常に新しい老いが重なり、多重構造を作っていくらしい。老いのまた老いを重ねながら人は本当に老いていくのである。
老いの中の老い、入れ子のように組み込まれているのが、実は生物学的に見た老いでもある。老いは、「全体的にとらえること」によってのみ理解しうるものである
老いの研究においては、精神、神経、内分泌、免疫というシステムとしての老い、心臓、脳などの臓器としての老い、その組織レベルの老化、さらには細胞や細胞内の小さな器官、分子、遺伝子といった様々なレベルでの老化の解析を通してのみ可能であるが、ある種の物質における変化を、個体の老化と言う全体像に投影することは極めて難しいのである。多くの研究は部分現象の積み重ねであって、老化の本質に迫っているものはないといえる。全体は部分よりなるが、部分の変化と全体の変化が不連続であるということが老化の特徴である。
免疫の老化研究から分かったことは、老化の生体変化の持つ「多重性」「不規則性」「不連続性」であり、これは個体発生や分化といった従来の生物学の対象が持っている「規則性」「連続性」といった生命の神秘、「造物主思想」とは対蹠的な統合性を欠いた反生物学的な現象なのである。生物学が普遍的な生物現象を扱うものとすれば、老化は決して普遍的ではなく生物学的現象ではないということになる。
それは結論的には、「生物が規則的で連続的な被造物である」という思想を捨てることを示唆しているのかもしれない。
老いのこころ―精神の老化について
年を取ると、こころにもある変化が起こってくる。例えば物忘れが多くなったり、学習能力は若壮年期に比べると低下して来ることも事実である。しかし身体の生理的老化に比べると精神の老化による変化はそれほど目立っておこるものではないようである。判断力、理解力は得意分野ではむしろ磨きがかけられ老練、老熟という粋に達して来る。
老年期の精神の変化は、単に加齢によって心理状態やこころの在り方が変わるというより、これまでの生きてきた個人の歴史的な集積による個人的な要因や共通する一般的な様々な要因が背景にあって老年期のこころは変化をとげる。
老年期の心理に共通する一般的な要因
身体病・不健康:心身相関、心身一体ともいうように、心は身体の鏡のように身体の影響を受けるが、老人ではより顕著に現れる。感冒が原因でうつ状態になったり、骨折や手術がきっかけで認知症が発症したり進行することは稀ではない。
1.脳の器質的な変化:脳神経細胞は再生しないとされ、加齢と共に減数して行くが、その程度は一律ではなく個人差が大きい。老年期に入ると、神経細胞の変性が起き、認知症になって行く。あるいは脳血管の老化によって脳萎縮が起きる。
老年期では、この様に脳の変化によって、脳の機能が減退し、認知機能は衰え、欲望や感情の表出も変化する。
2.老年期の喪失体験:老年期には①身体的健康の喪失②経済的基盤の喪失③失職による社会的役割の喪失④親しい人との死別、など多くの喪失体験を重ねる。喪失体験にはそれに対する怒り、抵抗、諦め、絶望の感情を収める悲哀の作業がいるが、老年期ではいくつもの喪失体験が重なってくる上、状況の変化に対応する予備能力が少なくなっているので、精神的に影響を受けやすい。
知能の老化
精神の老化で最も良く研究されているのが知能の老化である。
知能は知識を操作する能力で、過去の経験からの集積された知識を基礎にして、毎日の生活に起こってくる多様な問題を判断して解決してゆく能力である。
知能は記憶、理解、判断、計算、推理、学習能力など多くの要素からなり経験や知識に追うところも大きいので、仮にそれらの一部の要素の能力が衰退しても総合的な知能は、老年になっても容易には衰退しないと思われる。
知能は旧来の横断法の調査では20歳をピークにして加齢とともに急速に低下し始めるとされていたが、縦断法では知能の発達のピークは成熟期の後まで延び、衰退は60歳を過ぎてからとなった。さらに最近の縦列法では中年後期から初老期までは上昇傾向を保ち、60歳を過ぎてようやく衰退しはじめることが明らかになった。
一般的には、老化の影響を受けにくい知能要素は、言語数、情報量といった知識、言語性知能であり、衰退しやすいのは速度要素のある知能効率や動作性知能である。従って、「知識は精神を若返らせる(レオナルド・ダ・ビンチ)」と言われるように、知識を増やし衰退しにくい知識性知能の増加に努めることは、精神を若返えらせる論理的な方法になる。
知能の老化に影響を与える要因では、性差では男性の方が老化しにくく、教育歴では教育水準の高いほど衰退しにくい、身体健康では身体的活動性の高い人ほど知的水準も高いなど、老人の知能に影響を与えるもっとも強い要因は身体健康であるとされる。
老年期の感情
感情は知能と違って非合理的な主観的な世界の出来事であるから、知能の湯に一定の法則や傾向は認めにくいので老化による感情の研究はほとんど無いといえる。しかし感情においても老年になると変化が起きるのは確かである一定の傾向はみられる。
快・不快の感情は加齢とともに減弱する。運動や性行為の快感は弱くなるが食べることの快感は余り減弱しない。恋愛への情熱や新しいものへの情熱は、烈しさや強さは少なくなり、喜び、悲しみ、怒りという情動も激しさは弱くなり心の動揺も少なくなるが、情動のアンバランスが起きると消えにくく「うつ」や身心症になりやすい。
老年期の意欲
人間を行動に駆り立てる原動力は意欲であるが、年を取ると若い時に比較すると、意欲は落ち形を変えていく。
食欲は、量は減るが、食べたい良くは衰えない。性欲は、フロイトが指摘したように生きる本能・エロスの中核で老年期にあっても精神生活の重要な源泉になりうるものだが、個人差がより大きい。一般に若い時に精力的な性生活を送った人ほど、老年期にも活発な性生活を送る傾向があり、また老年になっても性意識を持ち続ける人は、性生活に限らず様々な人間関係でも活気に満ちた豊かな精神生活を送るとされている。
老年期の性格変化
年を取って人柄がすっかり変わってしまうことは多くはない。青年期までに作られた性格はその後の社会生活で次第に固められ成熟氏。老化で若干の微妙な変化が付加されるのが普通である。
起こりうる性格変化には、1)円熟化;若い時の特徴が目立たなくなり、角が取れ丸くなる、社交的、調和的になる2)先鋭化:抑制がとれ、若い時の性格特徴がますます拡大化し著明になる3)反転・反動化:若い時の性格と全く逆の性格になるまれな例。敬虔な信者が放蕩にふけるようになる。
性格は人間が生きて行く上での一つの防衛戦略でもあり、老年期になると、本来の性格に基本的な所は変化しなくとも、その内容に変化は起きているのは自然なことである。人間は四十を過ぎたら自分の顔に責任を持てと言うように、性格にも同じようなことが言えるのではなかろうか。人は成り行き任せに生きていたのでは老醜に陥るだけだともいえるようだ。
老年期の適応について
老人の生活適応で障害になるのは自己中心性と硬直化が挙げられる。自分本位で指示に承服出来ない、柔軟に対応出来ないのである。それは人間の心理生活にある「縄張り行動」という現象が、老化による行動制限から縄張りが狭く固定され、それに集中するあまりに、新しいことへの尻込みを招き、適応の硬さや自己中心性として現れてるともいえる。老年期に入ったらなるべく関心を広く持つようにし、縄張り行動を努めて広げるようにすることが大切になる。
また人間の心理体験には夢中になって仕事や遊びに没頭する「没頭体験」と、客観的に分析する「見通し体験」の二つがあるが、老年期では次第に没頭体験が減り見通し体験がおおくなる。従って、仕事でも遊びでもようから没頭体験を持つことが、老年期の精神生活を豊かにする。
老年期の生きがい
1.生きがいとは何か
生き甲斐とは仕事とか貯蓄とか、生きがいの対象になっているものと、生きがいを感じいる精神状態であって、生き甲斐を感じる強い喜び湧きあがてくるような感情を言う。立派な社会的地位を持ち物質的にも豊かな家庭生活を持ちながらも、心の底では虚しさが募り生きがいを感じられない人、反面、地位もなく貧しい労働生活に追われながらも、自分の生活に意義を見出し、些細なことに愛情を感じてしみじみとした生きがい感を持つ人もいる。
つまり生きがいの対象が生きがい感を作ると言うよりも。私たちのこころが、その対象とあるかかわりを持った時に、それは生きがいになるのであろう。
2.生きがいを妨げるもの
1)老年期の生きがいで問題になるのは、生きがいの対象になるものが、次々喪失して行くことである。
2)存在の様式に生きがいが見つけにくくなっていること。青年期の生きがいは目標に向かって進んで行く、goingの形にあるが、高齢期の生きがいは、他者と一緒にいる、共に生存するbeingの形にある。適応能力の減退した老人にとっては、環境が精神面に与える影響は無視できないものであり、老人の生きがいの問題を単に老人の主観やこころの問題に帰することは出来ないから、今の日本の社会の在り方はこれに逆行しているといえる。
3)老人は死を身近に感じながら、今まで生きてきたことを振り返るものだ。「自分の一生は果たして生きがいのあるものであったか」「自分の人生はこれでよかったのか。ほんとうにしたかったこと、すべきことがあったのではないのか」と。自分が未だしたかったこと,生きたいことが死によってさえぎられるのだから、人によっては生きがいが奪われると感じられるだろう。
4)エリクソンは老年期の自己像の受け入れは「統合性」で表現されると言っている。
エリクソンの「老いつつある人」で、「ものごとや人間の世話をしてきた人、他の人間を生み出したり、ものや考えを作り出し、それに伴う勝利や失望に自らを適応させてきた人―そういう人においてのみ、これまでの七段階の実が次第に熟して行く。この事を言い表すのに統合integrity以上にいい言葉を私は知らない。それは自分の唯一の人生周期ライフサイクルを代替不能なものとして、まさにそうあるべきものであったとして 受け入れることを意味する。なぜならば一人の個人の一生は単なる一つのライフサイクルが歴史の一コマと偶然にぶつかったものに過ぎないことを、こういう人はよく知っているからである。」
このように「老いつつある自分」を全体的に受容出来た人には、「英知」「知恵」という徳または力が現れるとエリクソンは言う。
「英知」とはすなわち死に直面しても人生そのものに対して「執着の無い関心」を持つことである、これの備わった人間は心身の衰えに拘わらず、自己の経験の統合を保ち続け、後から来る世代の欲求に応えてこれを伝えるが、しかも「あらゆる知識の相対性」を意識し続けている。-もし、知的能力と共に責任を持って諦める能力を併せ持つならば、老人達のうちには、人間の諸問題を全体的に眺めることが出来る人がある。これこそがintegrityの意味するところである。「このような自我の統合」に達することが出来なかった老人は、もはや人生のやり直しがきかないという「絶望感」を持ち、人間嫌いになったり、絶えず自己嫌悪に陥ったりすることが臨床的に観察されるとエリクソンは加えている。
これについて、神谷美恵子は次のように解説している。「成人は自分の生み出したものに対して責任を取り、これを育て、守り、維持し、そしてやがてはこれを超克しなければならない。」つまり、老年になってからは、自分が一生の間に「世話をし」、守り育ててきたものを相対化し、客観化しなければ「人間の諸問題を全体的に眺める」ような「統合」に達することが出来ない、というのがエリクソンの考え方なのだ。一生をかけた事業、学問があれば執着も大きいだろうが、自分の過去についての見方も、突き放して見る習慣を養っておかねば心の安らぎは得られないだろう。自分の過去についてこそ、エポケー判断停止が必要とされている。
つまりどのような仕事、学問、業績を生きがいにしてきたにせよ、すべては時と共にその様相も意義も変わっていくものだ、自分の後から来る世代によってすべてが引き継がれ、乗り越えられ、変貌させられて行く。その変貌の方向も必ずしも進歩とは限らない。分散か統合か、改善か変革か廃絶か、歴史の動向と人類の未来は誰が予見できようか。自分の過去の歩みの意味も自分はもとより、他人にもどうしてはっきりとわかることがあろう。その時その時精一杯に生きてきたのなら、自分の一生の意味の判断は、人間より大きなものの手に委ねよう。こういう広やかな気持ちになれば自分の過去を意味づけようとして、やきもきすることも必要でなくなる。徒に過去を振り返るよりは、現在周りにいる若い人たちの人生に対して、エリクソンの言うような「執着の無い関心」を持つ事も出来よう。彼らの参考になるものが自分にまだあるなら、喜んで提供するが、彼らの自主性をなるべく尊重し、自分は自分で、命のある限り、自分に出来ること、なすべきことを新しい生き方の中でやっていこう、という境地になるだろう。
自分の人生を振り返り満足できると危機感を感じないで幸福に人生を終えることができるといい、すなわちそれが統合、完成であるが、それには宇宙という大きな秩序の中で自分を捉えることで達成されるとエリクソンは言う。
健康に幸福に生きてきた人の心は、そういう満足と感謝の境地にいたるもので、死んでも死にきれないという人や、未だ人生に感謝できないと言う人は、きちんと老年期を迎えていないのだ、という。最後に問われるのは、「人生に感謝できるか」が課題となる。感謝できる人は危機感を持たずに死んでいける。感謝出来る人は年を取ることを受け入れることが出来る。
この宇宙観に通じる、神谷美恵子の素晴しい文章があるので、それを紹介する。
老いて引退した人間の最大の問題の一つは、社会的時間の枠が次第に外されていくところにある。体内時計の回転は遅くなっていくうえ、周りからの押し付けられる時間の圧力が減ってくると、うまく時間を自主的に支配するのが難しくなってくる。このことを良く覚悟したうえで、自主的に自分なりのペースで生きる時間の用いかた、配分の仕方を考え、超時間的に時間を観ずることが出来るようになるのが望ましい。そうすれば自分の一生の時間も、悠久たる永遠の時間から切り取られた極小さな一部分にすぎないことがわかるであろう。
自分は自ら志願してこの世に生まれてきたわけではない、この永遠の時間の一部分を意識して生きる人間存在になろうと願い出てきたわけでは無かった。しかし生まれたからには与えられた時間を精一杯生きてきた、時間を充実させて、なるべく良く生きようとは努めてきた。しかし、自分の一生には多くの若気の至りや過ちや「もっと良く出来たはず」のこともあるだろう。他人が自分をどう見るかは大した問題ではない、その他人もまた死んで行くのだから。
それより自分こそ、自分の一生が完全無欠なものでは無いことを知っている。ましてや、もっと大きな目から見れば、自分の一生などなんとおかしな、滑稽な憐れむべきものであろう。それにもかかわらず今まで人間として生きることが許され、多くの力や人によって生かされてきた。生きる苦しみもあったが、また美しい自然や優れた人に出会う喜びも味わえた。そしてこれからも死ぬ時まで許され、支えられて行くのだろう。これからも自分が意識するとしないとにかかわらず支えられて行くのだろう。永遠の時間は自分の生まれる前にもあったように自分が死んだ後にもあるのだろう。人類が死に絶えても、地球がなくなっても、この「宇宙的時間」は続くのだろう。自分は元々その宇宙的時間に属していたのだ。だからその時間は自分の生きている間も自分の存在を貫き、これに浸透していたのだ。
時間を一つの流れに例えるのなら、岸辺に在ってその流れを見ている観察者を想定しなければ成り立たない比喩だという意味のことをメルロー・ポンティは言ったが、厳密な意味では人間はその観察者たりえない。人間は流れそのものの一部なのだから。誰かが観察しているとすれば、それは「神」か何らかの超越者だろう。
私は神谷の言う超越的存在は、何も形を持った有機体を想像しなくても良いのではないかと考えている。それが、私が自律統合性機能autonomous integrity funcionと呼ぶような超越的な宇宙統制システムであるとすると、神ではなく私の宇宙観でも良く説明できる。
深沢七郎の楢山節考でも、「死を受容できることは、結局生も受容できることであり、自分の生きがいが、死によって奪われるとしても、残された時間を新しい生きがいで生きていくことが可能であり、老人にはその力があることを知るべきであるとして、老人を弱いものとしてだけ見るべきではなく、そのような生きがいに指示を与えて行くのが周りの人びとの責任であるとしている。
3.生きがいの追求.
年を取ると、生きがいの対象を見つけたり、生きがいを感じるような気持ちになる状況は次第に少なくなる。寝たきり状態で孤独な状況に置かれる場合でも私たちは生きがいを持つことが出来るであろうか。
フランクルはアウシュビッツの極限状況の中で生き延びた人々が「生きることの意味、生きること自体に目的を持ち生きがいを見つけた人であったと記している。
生きることは繰り返しの出来ない一回きりのものであり、かつ他の何人によっても代行できない独自のものである。(人生一回性と独自性の自覚、生きていること自体に生きがいを持つ)
自分の人生を振り返り満足できると危機感を感じないで幸福に人生を終えることができるといい、すなわちそれが統合、完成であるが、それには宇宙という大きな秩序の中で自分を捉えることで達成されるとエリクソンは言う。
健康に幸福に生きてきた人の心は、そういう満足と感謝の境地にいたるもので、死んでも死にきれないという人や、未だ人生に感謝できないと言う人は、きちんと老年期を迎えていないのだ、という。最後に問われるのは、「人生に感謝できるか」が課題となる。感謝できる人は危機感を持たずに死んでいける。感謝出来る人は年を取ることを受け入れることが出来る
自分は自ら志願してこの世に生まれてきたわけではない、この永遠の時間の一部分を意識して生きる人間存在になろうと願い出てきたわけでは無かった。しかし生まれたからには与えられた時間を精一杯生きてきた、時間を充実させて、なるべく良く生きようとは努めてきた。しかし、自分の一生には多くの若気の至りや過ちや「もっと良く出来たはず」のこともあるだろう。他人が自分をどう見るかは大した問題ではない、その他人もまた死んで行くのだから。
それより自分こそ、自分の一生が完全無欠なものでは無いことを知っている。ましてや、もっと大きな目から見れば、自分の一生などなんとおかしな、滑稽な憐れむべきものであろう。それにもかかわらず今まで人間として生きることが許され、多くの力や人によって生かされてきた。生きる苦しみもあったが、また美しい自然や優れた人に出会う喜びも味わえた。そしてこれからも死ぬ時まで許され、支えられて行くのだろう。これからも自分が意識するとしないとにかかわらず支えられて行くのだろう。永遠の時間は自分の生まれる前にもあったように自分が死んだ後にもあるのだろう。人類が死に絶えても、地球がなくなっても、この「宇宙的時間」は続くのだろう。自分は元々その宇宙的時間に属していたのだ。だからその時間は自分の生きている間も自分の存在を貫き、これに浸透していたのだ。
老年期の特徴
老年期は個人差が大きいことが著しい特徴だが、それは生物学的要因と共に社会的要因が大きいためであり、もう一つは人間には精神・心をもっているためである。心の世界を持つことによって人間は老年を貧しくも豊かにも生きる可能性が与えられているのである。
老年を語る様々な言葉
*老いるとは一つの決断だ、老いるということはある種の潔さを身につけることだ。(折原脩三)
*老いることに、どうしてこれほど臆病になってしまったのか。根本は金の問題ではない。老人が甘えてしまったのだ。老いる前に自分で命を節約して生きることになれてしまったからである、思い切って命を浪費してみたらどうだろう。
社会が規範として押し付けている観念に、余りもがんじがらめにされてしまっていないか。自分自身のこころで人生を生き、自分自身のものとして老いを受けとめれば、「老いる」生が深々生きられるはずだ。(折原脩三)
*老いるに「救い」などあるはずがない。ただ生きざまがあるだけなのである。(折原脩三)
*老いは生きている限り誰にでも訪れるという意味で「自然な過程」であるが、老いとの出会い方、老いへの向き合い方は一人一人異なっている。人と老いとの出会いの場にはそれまでの生のすべ手が流れ込み、その人にとっての「意味場」をつくる。Dそれは、思想とか哲学とか宗教とといった、ありきたりの言葉や概念ではとらえきれない、もっと根源的なものだと思う。(澤村光博)老いとの出会い、自分なりの意味場を持つようになった時、不意に穴が開いて、若い時には見えてこなかった独自の世界が垣間見えるような体験を持ちましょう。
*老いは、自然の過程として誰の肉体にも一様にやって来るが、老いの迎え方は人間ごとに異なる。そこには人の、これまでの生き方のすべてが集約が現れる。
*人間など大仰に騒ぐほどのものではない。宇宙的空間の中で「一個の人間が老いる」ことなどにどれ程の意味があるか(立花隆)
*秋の日は濃し春も濃かりしが。高浜虚子(老年もなってみると、青春に劣らず味わい深いものだ)
遠山に日の当たりたる枯野かな 高浜虚子(我が人生は日の当たらぬ枯野のごときであって良い。むしろそれを希望する。ただ遠山の端に日が当たっていることによって、こころは平らかだ。)
*人間が老いるということは、己の生きてきた人生の長い一線を手近な所からゴム消しで消していくことで、これは老人の意思ではどうにもならぬことである。老人にとっての過去というものは、そこに存在理由を、生きる意味を持っており、過去を語ることがその時間を生きているということであり、過去を語らせることが必要なのだ。
*日々死に直面しつつ生きる老人にはある種の強みがある、この強さは自律的精神に基づいており、肉体的には衰えていても精神的には、そこか芯の強いところがある。シレは「しぶとさ」とか「したたかさ」とか形容したいものである。あるいは「意地」といっても良い。自律的精神を本当の意味で持つ老人は「従容として老年の衰えを甘受し、日々死と直面しつつもなお生き続けるのである。(土居健朗)
*老人には存在すること自体に価値がある、日常当然のように考えている価値観に疑問を投げかける存在としての老人に意味がある。老人の無為が存在することの重みを教えてくれる。(河合隼男)
*これから世の中に出ようとする孫と世の中から引退した祖父母、言いかえれば新しい命と消え去ろうとする命が現に働いている両親を軸に対称性を持ち出会うことが必要である。(井上ひさし)
*生きることは実は死ぬことであり、死ぬということは生きることである、死ということを考えるようになって初めて生きるということの意味が分かるのではなかろうか(高島善哉)
どう向き合うか
老化は生理的にも精神的にも多様性に富み、個体差が非常に大きいことが明らかになった。
いえることは身体的老化も精神的老化も確かなものは何もないということである。
実に老化とは、「なってみないと何も決まらない」と、まるで量子論を思わせる現象なのである。
では老化はなすが儘に任し、何ら対策を取る意味はないのであろうか。
老化とは基本的にはエントロピーの増大であるから、対策は2つである。一つはエネルギーを入れてエントロピーを減らすこと。もう一つはエントロピーの増加を極力抑えること。
増加を抑えるには変化を定常化させ極小化を図ることであるから、恒常性ホメオスターシスを働かせることである。
つまり自律統合性機能を高めるように心身を鍛えるのが論理的な帰結になる。
マインドフルネスでレジリエンスを高め、レジリエント生活・食事療法で恒常性の強い身体的健康を図ることが有効になる。
こころの老化は、知識として学ぶことはできる。文学、哲学から今日的マスメディアまで老化の情報は溢れている。しかし受動的にそれを読み聞きするだけで老化することを理解でき、老年期の悩み・危機は回避できるだろうか。
言葉を蓄積してみても仕方がない、それを知リ身につけることが老いるということだと思う。
自ら語りて自らの老いを知り、統合性をはかることが老いの悩みの解決につながるのではないだろうか。
自らの人生を語ることで、今の自分の本当のところ、悩みの真実を知り、気持ちも楽になるのではないか。
当クリニックでは、どんな些細な悩みでも、人生観、自然観につながる深い悩みでも、何でも傾聴し、共に「生きることについて」語り合います。