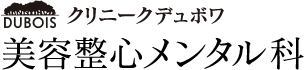新しい心の捉え方
心は肉体とは別に存在し、死後も残るという霊魂の考えは世の東西を問わず、古代より信じられてきたことですが、自然科学が実証主義で進歩してくると、「心はどこにあるのか、物なのか」と言う身体と心の関係が問題になりました。心は脳にあると考える事だけは、多くの人に異論が無くなると、この問題は心脳問題と言うようになり、今日まで着解決な問題として引き継がれています。
心が脳と言う物質というならば、逆説的に言うと「物質モノとは何か」が、はっきりしなければ心も見えてきません。この物質とは何か、を極めようとしているのが量子論であり、従って心を量子論で見ようとする動きも当然出てきます。
現在の心脳問題はどこまで問題を解決しているのか、を量子論との関係の中で見ていきたいと思います、
1.心脳問題が教えてくれたこと
「人間の心はどこにあるのか?心は物であるのか?心と身体とはどんな関係がるのか?」などの疑問を哲学では『心身問題」といい、人類が誕生し、自分たちの心というものに気づいてから悩み続けてきた問題であり、伝統的な哲学的な、未解決問題でした。科学者が心の問題に関わるのは、キリスト教的な世界観の中ではタブーとされて来ましたので、科学がこの問題に関わるようになったのは近年以降のことです。
現代の理解では心が「脳」にあることは、まず間違いないという合意事項となりましたので,「心身問題」は「心脳問題」と言うようになりました。
私達の身体は分子、原子、さらには量子、素粒子、DNA、RNAなどの物質から成り立っています。
物質は合成して作ることが出来ますが、生命は作ることが出来ないことから、心脳問題は「生命とは何か?」という、もう一つの大きな未解決問題とも底辺では繋がっていると思われています。
心の問題はギリシャ時代から、一元論、2元論の2つに分けて考えられ、それは形を変えつつも現在に至っております。
二元論は、「心」と「身体」を別のものとみなす考えで、肉体から離脱した「霊魂」を考える有史以来のもので、それは中世までは宗教的な理念とも両立できてきましたが、自然科学の進歩の中で、実証主義が人間の理性を主張し始めると、キリスト教的世界と融和してきた二元論の根拠が必要になってきました。 デカルトは徹底した懐疑主義から「コギト・エルゴ・スム(われ思うゆえに我あり」を唱え、「考えている自分の存在(身体)」と「自分が考えている事実(心)」は二つに分けられるとし、心身二元論をうまく説明しました。
デカルトは、心は脳と異なり物質的実態のないものであり、古来から生命の根源とされて来た気息(ティモス)の考えを延長させ、気息は脳の松果体に宿り、神経伝達物質の様に全身をめぐるとし、脳の松果体を通して、心と体がつながって作用(心が脳を制御する)しあうという「相互作用説」を述べました。
デカルトがなぜ松果体を持ち出したかと言うと、当時の解剖学では脳の正中に一つだけあるのは松果体であるという理解からきているようです。は人間の脳にしかなく、さらに脳の正中に一個だけ存在していることを根拠にしているにすぎないという。デカルトは客観と主観の仲立ちとして神を持ち出したように、どうも、交わらない二つの領域に仲介者を立てる論法が好きらしい。しかし、松果体は物質としての脳の一部であるし、気息がどうやって心を生み出しているかの合理的な説明はなされていない。これは、心があるのは、脳の中に小人が居て、いろいろ働くからだと言うものの、今度は小人の脳と心の問題はどうなるかと、問題が循環され無限に繰り返す「ホムンクルス問題」と基本的に変わらないことになります。
二元論は、現代においても引き続き存在しています。
オーストラリアのチャーマーズは、まず物理的な脳の活動がって、その活動に心が付随しているという「随伴説」」を述べているが、心と脳の関係性メカニズムについては説明していません。
チャーマーズは「哲学的ゾンビの話」という思考実験で一元論の還元主義を否定していることで有名で、それは、『見た目が人間なのに心を持たない存在(哲学的ゾンビ)がいたとしたら、還元主義は「こころを持つ存在(私達)」と区別つきますか?』というものです。
これは、他人の脳を移植をすれば他人の心も移植されるのかと言う話にも繋がりなり、形成外科医としても大変興味深い指摘です。
ノーベル賞受賞脳科学者のEcclesは最新の脳科学の知見に基づく「心脳相互作用説」を提唱していますが、これはかなり面白い考えです。
自由意思(自我)が脳とは独立して存在し、脳の補足運動野に働きかけニューロンが生まれ自発的な運動が起きるといいます。脳と独立した自我が、どのように補足運動野のニューロンに働きかけるかについては、カオスの揺らぎ理論と言う最先端の物理学で説明しています。自我は大脳のプログラマーであるとし、補足運動野が脳と自我を連絡する「連絡脳」であるとする、つまるところは、デカルトの松果体の相互作用説と大差ないような説であり、多くの脳科学者は賛成していませんが、ペンフィールドなど少数ではあるが支持者もいます。
一元論は、ヒポクラテスが「心は脳の営み」と提唱したことに始まります。
プラトンもそれを支持しましたが、アリストテレスはプラトンを否定したことや、キリスト教の影響で、一元論は広まることはありませんでした。
近代になると、二元論を支えてきたましたが、心理学の行動主義が終焉し、神経科学の発展が「心は脳の活動である」とする一元論、特に還元論的唯物論の勢いを強めることになりました。
自然科学の発達は、この世のものはすべて物質で出来ているのだから、脳の物質を究明すれば心もわかるはずであるという考えをもたらし、神経細胞の集団の営む過程が心の働きであり、集団全体の持つ状態が精神状態を示すとし、脳神経細胞の発火によって心が生まれるのであって、心も物質に還元されるという還元論的唯物主義が生まれた。
しかし神経細胞と神経伝達物質の作用がどんなにわかっても、それが心であるという説明には至っていないのです。唯物論で証明するには、自然現象を数式で明らかにした物理学の様に、心の数式を見つけて、それが現実に観測される心の状態と一致する事が必要であり、また心の方程式に変数(電気や薬品などによる刺激)を入れると予想通りの心の状態が現れてこそ物理理論で解いたことになり、還元論的唯物主義が正しいことになります。
しかし、そうなると、まさしく心が因果律で説明されることになり心には自由が無く、自由意思を一切否定することになってしまいます。
例えば、ある薬を与えると誰かを好きなる気持ちにさせる、食欲を起こさ
せなくするという、夢の「惚れ薬や痩せ薬」が現実になり、自由意思が奪われてしまいます。もっとも痩せ薬は食欲中枢を抑えるという神経反射のコントロールであり現実的になって来ていますが、人に惚れるというのも神経反射でないとは言い切れませんので、そんな将来がありえないとは言い切れませんが、もし、そのような自分の気持ちが自在にコントロールされる時代を皆さんはどのようにお考えですか?
もう一つの一元論が心脳同一説であり、これは心と脳は同じモノであり、同じモノが心に見えたり、脳に見えたりするという考えで、丁度、量子物理学で、光が波であったり粒子であったりする、のに似て魅力的な発想ではありますが、量子を説明した量子論のような概念は心脳問題ではまだ見つかっていませんが、何処かで誰かに、暗黙知が生まれ創発が起きないとは限りませんので、私はこの説には魅力的に思えます。
現在では、当然のように、自然科学的なアプローチである唯物論の研究者が最も多く、「クオリアの概念」を日本に広めた茂木健一郎も、脳の中の分子は物理法則によって動いている、脳に意識が宿ることによって分子の動きが変わることはないし、人間には本当には自由意思はないという意見であり、ニューロンンの発火が心を支えており、一つのニューロンの発火の様式を決めるのはニューロン同士の結合のパターンである、と言っています。
しかし観念論に近い一元論も現代でも存続しています。
哲学者の大森荘巌は「無脳論の可能性」で脳が無くとも心はありうる、と述べているし、一方養老猛司は「唯脳論」を言っています。
還元論的唯物論を支える理論の一つに量子論があります。
量子力学が成立した極初期の頃から、一部の物理学者達は量子力学と意識は関連しているかもしれないと感じていました。
還元論的唯物論は心も物質で成り立つという立場ですが、そこで、物質とは何かを明らかにする必要があります。、次章では量子論を簡単に説明し、心とのつながりを見てみようと思います。
るが、これらに関しては竹内薫と茂木健一郎が訳と解説をした「ペンローズの量子脳理論」(徳間書店、1977年)が詳しく、面白い。
心に関して量子論的な考察をした人には、神経生理学の立場からは先に述べたEccles、哲学的立場からはRockwood がいる。(「心身問題と量子力学」、産業図書2003年)
また、量子論はその哲学的観念から唯我論的一元論を導いたが、これはBurgeの分類では観念論に入ると思われる。量子論の哲学的意味を考えるに面白いので紹介する。
まず、量子論は以下の事実を明らかにした。
- ① 光は波動性と粒子性を持っている。
- ② 電子も波動性と粒子性を、持っている。
- ③ 一つの電子は複数の場所に同時に存在できる。(電子の状態の共存性④電子の波は観測すると瞬間に一点に縮む。(電子の波束の収縮性)⑤電子の状態は曖昧である。(電子の不確定性原理)
そして量子論は次の3つのパラドックスを持っている。
①ミクロの世界では、ニュートンの法則には従わない。なぜなら、マクロの世界では物体の運動は連続するが、ミクロの世界では電子の運動は連続しないから。
②ミクロの世界では、観測者の意識が観測対象に変化を与え、観測対象そのものを変化させたり,創造したりするが、マクロの世界では観測者の意識が観測対象に変化を与えることはない
④ ミクロの世界は確率の世界で、すべてが確立的に決まる。つまりマクロの世界の因果律はミクロの世界では全く通用しない、事になる。
唯物論で心脳問題がなかなか解けないのは心が数値化、定量化、客観化できず自然科学のやり方がうまく通用しないためです。
心脳問題を解くには、全く新しい技術や方法論を使った科学が生まれなければならないだろうと言われますが、今、可能性のひとつとして「暗黙知と創発の概念」が言われています。
創発とは「カオス理論」や「複雑系」といった学問領域で使われる概念で「たくさんの『部分』が相互作用することで、『全体』としての新しい作用が生まれる現象』のことで、全体の性質は部分の性質の集合だけでは決まらないとも言うことができます。脳を構成する一つ一つの神経細胞の振る舞いの知識を組み合わせるだけでは心は説明できず、単純な振る舞い(部分)が複雑に組織化され、心(全体)が創発されると考えるわけです。暗黙知とは、ヒラメクときに身体の中におきるプロセスや活動、メカニズムのことで、「部分に注目したら、いつの間にか全体が見えてしまう。」というような構造と説明し、「部分から全体へ」創発が起きる時に働く力のことをいいます。
この概念を用いてBungeは創発的一元論を提唱しています。
これはBungeが意識・心を脳の特殊なプロセスとして考え展開した理論であり、心・意識は一個のニューロンに還元出来ず、システムとしてのニューロン群が活動しプロセスを進行することによって心・意識が形成される、とするものです。
そこでは異なる脳の部位で分散的に処理された情報がどのように統合されるかという問題が生じ、それは「結合問題」あるいは「統合問題」と呼ばれ、脳科学の重要課題になっています。
現代の脳科学者は、多くはこの創発的一元論の立場に立って研究しています。ある心の動きが一個のニューロン、や単一の脳部位で実現される、還元されるとは殆ど誰も考えていません。むしろある心の働きは、多数のニューロン群や脳部位が形成する「階層的並列システム」の働きによって形成されると考えています。
一時期はやった「おばあさんニューロン」などと言う、認識を単独で担うニューロンの存在は今は信じられてはいず、創発的一元論が主要な立場になっています。
ところで、脳科学者が自らの研究を‘意識や自我’という心理精神医学的な表現に立ち入ることは殆どありませんでした。しかし最近は、脳科学の進歩から、哲学、精神医学、心理学の出口の見得ない方向性を正す意味からも、脳科学者の発言が始まったように見えます。
Damasioは『デカルトの間違い』でデカルト流の二元論を正面から批判し、DNA二重らせん構造でWatsonとともにノーベル賞を受賞したCrickは、その後脳科学に転じてから、意識のサーチライト仮説など多くの独創的仮説を述べ,著書「驚異の仮説」の中で「意識とは多数のニューロンの集まりと、それに関する分子の働き以上の何ものでもない」と表明しています。しかし、それは今や脳科学者の間では驚異でもなんでもなく、最大公約数的なセントラルドグマとなっています。
現代の脳科学者の心脳問題におけるコンセンサスは、「意識も自我も他の心の働きもプロセスであり、脳の働きもまたプロセスである」とし、脳内プロセスはニューロンやその集団(セルアセンブリ)のダイナミクス(相互作用やそれによる動的変化)をベースにした様々なプロセスである、と言うところにあるようです。
そして、脳の本質的理解には、ハードウエアとしての神経生理解剖学的な理解に加えて、(目的、理由を問う)計算論的なアプローチが必至であるとも言われるようになっています。
新しい心の捉え方―量子論が教えてくれたこと
最近何かと話題の再生医学は、生きた細胞、組織を作りだしますが、それが集まると、はたして宇宙が生んだ生命と同じものになりうるのか?また再生された人間、脳には心が宿るのかは、大きな興味があるところです。心脳問題を考える時、物質とは何か?を、まず知らなければなりません。それを明らかにするのは量子論です。量子論はノーベル物理学賞で、この分野で今世紀に入ってから日本人が相次いで受賞したので、比較的なじみのある言葉ですがそれが何であるかは案外理解されていないように思います。
物質ばかりでなく、心も量子論が関係するという見解も、最先端の自然科学者、量子物理学者からも出されているので、その意味するところを理解するためには量子論の概略を理解することは避けては通れませんので、本当にざっくりと説明したいと思います。
私はもちろん量子力学には門外漢ですので、数式を用いた物理学としては理解できていませんし、上手に要約してお話しする力もありませんので、文章の出典は佐藤勝彦と竹内薫の本であり、基本はそこからのコピ―アンドペーストである事を始めにお断りしておきます。
まず量子とは何だろう?を考えます。
私達の身体も地球上に存在するあらゆるものも、宇宙の星や銀河も、すべての物質は100種類ほどの原子(元素)から出来ています。そして原子はさらに、中心にある原子核(陽子、中性子、中間子と言う微粒子が複数集まって出来ている。)と、その周囲を回る電子から出来ていることは100年ほど前に明らかにされました。
その後、陽子、中性子を固く結びつけている、電子との中間の大きさの未知の微粒子、中間子の存在が明らかになりました。中間子を予言したのが湯川秀樹博士で、後にそれが実証されノーベル賞を受賞しました。
アインシュタインが光の正体とした光子も素粒子の仲間です。
素粒子は物質の素になる究極の微粒子とみなされていましたが、その素粒子もクォークという、さらに小さな構想物の組み合わせで出来ていることが明らかにされました。
。素粒子があつまると原子核や原子、もっと集まると分子になります。素粒子には電子、クォーク、ヒッグスなどの種類と名前があります。
例えば太郎、次郎、花子、藍、あやめ、等の名前があり、男、女、人間、猫のような種類があります。素粒子はナノの単位(10億分の1メートル)の物質で、ミクロの世界と言われます。このミクロの世界は、従来の古典物理学で支配されるマクロの世界とは別で、ミクロの世界独自の物理法則に支配されており、その法則を量子論と言います。その法則を数式で表したのが量子物理学です。
素粒子同士の振る舞いをくりこみ理論で説明したのが朝永振一郎で、クォークが6種類である事を予言したのが,小林誠、益川敏英など日本の理論物理学者です。
そのクォークも、さらに小さな「ひも」が様々な方向に振動することで作られるという超ひも理論が現在では有力になっています。
量子はエネルギーの量の小さな単位のことを言い、プランクが光のエネルギーの最小単位をエネルギー量子と言ったのが最初で、アインシュタインは光も粒子であるとし、光のエネルギーの単位を光量子としました。量子は素粒子のように小さくてエネルギーの最小単位が判別できる小さな塊の総称を言います。従って電子も、陽子もクォーツもヒッグス粒子も量子なのです。
ミクロの世界の住人である量子は奇妙な振る舞いをします。
この振る舞いを明らかにした量子論の歴史は、物事が革新的に進歩するときの思考の働き、心脳問題の所でお話しした「暗黙知と創発の概念」をよく表していて興味深いものです。
そこで、量子論の発達の大まかな流れを示したいと思います。
19世紀から20世紀にかけて、人類は究極の微粒子と考えていた原子がさらに分割できること、すなわち原子の中に電子が含まれることがわかってきました。そこで原子の内部構造に関心が集まり、「トムソンの原子モデル」というものが出来ました。
これは丁度スイカのように、赤い身がプラスの電気を帯び、種が電子に相当するようなイメージのものでした。
ラザフォードは、実験的に原子の中心部にプラスの電気を持つ重い粒子が存在(原子核)し、その周囲を電子が回っているという太陽系に似た「ラザフォードの原子モデル」を提唱しました。
実は、日本の物理学者の長岡半太郎もラザフォードのモデルに似た土星型原子モデルをトムソンより早く発表していたのですが、国内外で評価されませんでした。
しかしラザフォードの原子モデルには致命的な欠陥がありました。それは、当時の電磁気学でも、電気を帯びた粒子が回転運動すると電磁波(光)を発生し、粒子は運動エネルギーが減弱することが分かっていたので、電子はすぐにエネルギーを失って、原子核に引き寄せられ、原子は構造を保てないとするものでした。
そこでこの難題を解決したのがアインシュタインに匹敵する20世紀最高の天才物理学者といわれるボーアでした。
ボーアは、友人が教えてくれたバルマー系列にヒントを得て一気にこの難題を解決し、「ボーアの原子モデル」を完成しました。
ここに二つのヒントがあります。
バルマー系列はスイスの中学校の実験好きの数学教師が、真空放電させた水素が4つの線スペクトルを描き、その四つの光の波長の間にある規則性がある事を見つけて、数列にしたものです。
その数列を見たボーアはラザフォードの原子模型にそれをあてはめ、それが成立する為にはいくつかの条件を満たす必要があるとして、ボーアの量子条件を提案しました。その条件は理屈抜きのもので、「とにかく、その様に決まっているんだよ」と開き直るような都合のいい話でした。これらの条件はプランクのエネルギー量子仮説や、アインシュタインの光量子仮説を土台にしたもので、それにバルマー系列を組み合わせて、三つ以上のものを作り上げたのです。まさに暗黙知から創発に繋がったのです。
この理屈抜きのボーア条件に理屈を与え、解決したのがフランスの貴公子ド・ブロイでした。「光が波であり粒子である」ならば、「電子も粒子でありながら波であってもいいのではないか」と逆転の発想をし、その電子の波長の整数倍が電子の軌道の周径であれば、波は干渉されず電子は軌道にとどまることが出来、ボーアの量子条件を満たすことが出来るという、大胆な仮説でした。
ボーアの大胆不敵な発想を、理論的に解決したのもド・ブロイの大胆な逆転の発想でした。
ここにも単なる還元主義では出てこない創発が見られます。
ド・ブロイは物質はすべて波動としての性質を持つとして、「物質波」の概念を創りました。
物質波の概念に強い興味を持ち、物質波の伝わり方を計算する方程式を作ったのがシュレディンガーで、この方程式を解けば、物質がどんな形の波になっていて、その波が時間の経過とともにどのように伝わって行くか計算が出来ます。
これが現在でも量子力学の基本的な理論になっていて「シュレディンガーの波動方程式」と呼ばれています。
しかし、この物質波のシュレディンガー方程式が、虚数を含むことから、「この物質波とは一体何か」ということで、天下を二分するような大論争が展開されます。
一方で、電子が波であることはいくつかの実験で証明されたのです。
音波や光などの波動方程式は実数だけで出来ているので、波の高さ[振幅]は実数で示され実在するものとして認識されます。それでは、虚数を含む電子の波は実在しないのか、
あるとしたのは実在派と言われるアインシュタインン、シュレディンガー、ド・ブロイであり、電子は実在するのだから波動の実在が言えないのは波動関数が不十分な式だからだとしました。
ボルンはシュレディンガーの関数が示しているは、神様が振るサイコロのように、偶然性によって決まる電子の存在する位置の確率であるとしました。これを受けてボーアたちは「我々が電子を観察すると、電子の波は一点に収縮する。」そして「見ていないときだけ、電子は波のように広がっているのだ」としました。電子の波が広がっている時は、電子はある場所にいる状態と別の場所にいる状態が重なっていると考えました。そのどちらかにいるのだが、見るまではどちらにいるかは分からないが、見たとたんに波は収縮して電子はある点に発見されるというのです。
その場所はサイコロの目にのように、確率的に偶然の要素で決まるとし、「波の収縮」と「波動関数の確率解釈」を二本柱として、私達の見る前の電子と、見た後の電子の様子を解釈すればすべてが丸く収まる、と言うのがボーアたちの考えで、コペンハーゲン解釈と呼ばれるものです。理論による計算値が実験データと合って実証できれば、その過程はどうでも良いではないかとするもので、実証派とも呼ばれ、ボーア、ボルン、ハイゼルベルグ達がそのメンバーです。
ハイゼルベルグはシュレディンガーの方程式と同じ意味の事を行列の数式で示し、これを持って「不確定性原理」としました。これは電子の位置と運動量は、両方とも正確には測定できないとするもので、電子は衛星の軌道のように決まったルートを回るのではなく、ドーナッツの輪のような電子雲と呼ばれる輪の中のどこかに存在するとしました。従って量子の軌道と言う概念を否定するものでした。
アインシュタインはコペンハーゲン解釈に納得せず、神様はサイコロを好まない、と言う有名なセリフとともに、EPRパラドックスと言う思考実験で反論しました。シュレディンガーも物理学は決定論であり、電子の波は実在するとして、シュレディンガーの猫と言う思考実験を行い反論しました。
EPRパラドックスは粒子のスピンが保存されるには、情報が光の速度を越えて伝達される必要が生じるから、自然の摂理である相対性理論に反しておかしいとするものでしたが、アスぺは量子テレポーション(瞬間移動)の存在を実験的に明らかにし、ベルの不等式が成り立たないことでEPRパラドックスは成立しない事を明らかにしました。
天才アインシュタインはここでは一敗地にまみえたのです。
シュレディンガーの猫とは次のような思考実験です。
密閉された一つの箱の中に放射性物質と、それが核分裂を起こすと毒ガスが発生する装置と猫を入れておきます。コペンハーゲン解釈に従うと放射性物質の核分裂は、それが起きたかどうかは観察者が見るまで分からないことになるので、猫は死んだ状態と生きている状態が重ね合わさった状態になり、それは不自然ではないか、とするものです。
しかし、また逆転が起きます。
フォン・ノイマン(現在のコンピュータを作った人)はシュレディンガーの波動方程式は収縮しない事を証明します。
となるとコペンハーゲン解釈も成り立たないことになるので、コペンハーゲン解釈に寄らづに量子が波であり粒子である動きを説明する必要が出てきます。
そこで、にわかに多世界解釈が有力視されるようになりました。
多世界解釈とは、重ね合わせの状態を、その数だけの世界があるとみなすものです。
シュレディンガーの猫で例えれば、観察者が観察すると、死んだ状態の猫とそれを観察する観察者がいる世界と、生きている猫を観察する観察者がいる世界に世界が分裂してしまい、それらの枝分かれした二つの世界は互いにその存在を知ることは出来ないとするものです。枝分かれする世界は、量子が存在する可能性のある場所の数だけあるとします。
ここでは半死半生の猫の存在とか、波の収縮がいつ起きたとか、ミクロとマクロの境界がどうのと言うような問題は一才発生せず、パラドックスはどこにも見当たらないのです。
しかし、この『パラレルワールド』と言う概念は、「宇宙は一つ、世界は一つ、私も一人」と言う私達の常識的感覚からあまりに乖離しているために多世界解釈を取る科学者は少数派にとどまっています。
本来、解釈というものは実験的に証明されないものなので、解釈には正解はなく、結局どの立場をとるかというだけの事で、どちらが正しいということではないのです。
さて量子論の以上見てきた変遷の中で、量子論は以下の事実を明らかにしました。
- ① 光は波動性と粒子性を持っている。
- ② 電子(量子)も波動性と粒子性を、持っている。
- ③ 一つの電子は複数の場所に同時に存在できる。(重ね合わせ、電子の状態の共存性)
- ④ 電の波は観測すると瞬間に一点に縮む。(電子の波束の収縮性、瞬間移動、共時性)
- ⑤ 電子の状態は曖昧である。(電子の不確定性原理)
そして量子論は次の3つのパラドックスを持っています。
①ミクロの世界では、ニュートンの法則には従わない。なぜなら、マクロの世界では物体の運動は連続するが、ミクロの世界では電子の運動は連続しないから。
②ミクロの世界では、観測者の意識が観測対象に変化を与え、観測対象そのものを変化させたり,創造したりするが、マクロの世界では観測者の意識が観測対象に変化を与えることはない。
⑥ ミクロの世界は確率の世界で、すべてが確率的に決まる。つまりマクロの世界の因果律はミクロの世界では全く通用しない、事になる。
さてこのような量子論から私達は以下のような哲学的な観念を学ぶことが出来ます。
以上のようなコペンハーゲン解釈は以下のような解釈も可能にする。
① 不確定性原理から、確かなことは何もない、自然はすべて曖昧で非決定的である、ということ。月は私達が見たからそこにあるのであり、見ていないときはそこにはいないことになる。(アインシュタイン)量子論的には誰にも見られていないときは「様々な場所にいる」のである。量子論は客観的事実の存在を否定し、自然は観測によって初めて状態が決まるものであり、誰も観測していないときは何も決まっていない。
② 量子論では電子は様々な場所に広がって存在する波の性格と、一カ所に存在する粒子の性格を同時に持っているが、このように相いれない二つの事物が、互いに補い合って一つの事物や世界を形成しているとする考え方をボーアは相補性という言葉で説明しました。不確定性原理が示す「位置を決めると運動量が決まらず、運動量を決めると位置が決まらない」も相補性です。これは中国の陰陽思想に似ており、またユング心理学が示すタイプ論、意識―無意識、ペルソナ―アニマ、アニムスなどの相補性に通じるものがあり、心のシステムと量子論の構造には親和性がある事になります。
③ 近代科学は、物と心、自然と人間など対象と観察者を分ける二元論でしたが、量子論は観察対象と観測するものが一体関係にあるとし、自然観を二元論から一元論に移行する役割を果たした。
④ 量子論は量子のテレポーション(瞬間移動)の成立を明らかにしたことは、意識が脳神経細胞の重層、並列的な同期発火によって生じるとする最近の心脳問題や脳科学の知見や、ユングのシンクロシニティに親和性があり、心の成り立ちが量子論で解明される可能性がを示しました。
⑤ 単純な因果律、線型システムではなく複雑系、非線形的なメカニズムでこころが成立するであろうとする創発主義心脳論は、決定論的因果律を否定した量子論に親和性がある。
これらから心の仕組みが量子論に多くの親和性を持つことが明らかになったと思います。
つまり、万物や宇宙で起きる出来事は、すべて潜在的に存在していて、人間が観察しない限り決して実在しない。つまり人間が万物の創造者となるのである。私達が意識を変えることで宇宙を変えることになる。私たちの意識は自身の波動関数を収縮させることで変わる。つまり、宇宙は人間の心によってのみ存在する(ジョン・ホイラー)、宇宙は人間の心の化身(結晶化)である(ヒューストン・スミス)、人間こそは、森羅万象を決定する存在である、ということになる。これから量子論的唯我論ともいうべき一元論が導かれるのである。
量子論こそは従来の<物の世界の学問領域>を越えて、<心の世界の学問用域>にまで踏み込んだ<物心一元論>の真に創造的な学問ということができるのである。
新しい心の捉え方-心は波動であるー「精神波」の概念
先に見てきたように,心脳問題における現在の主流である還元論的唯物一元論では、こころにはニューロンが関与するとされ、ニューロンが直列的に信号を伝播し作動するのではなく、オーケストラがシンフォニーを奏でるように、ニューロンが並列,重層的に発火し共振するのではないかという仮説があり、そこには量子論の共時性(量子テレポーション)の概念が適応されるというのは説得力のあるところでした。
心に量子論が親和性があるとなると、量子論が証明してきた物質の波動性は心にもあっても良いのではないかというのが私の直観です。
ド・ブロイは電子のような物質粒子が波としての性質を持つとして、あらゆる物質には波動性があるとし、その波の性質を「物質波」と名付け、量子論の基礎を築きました。
私は、心にも波としての性質があるとし、物質波に対比して「精神波」の概念を提唱したいと思います。
そこで、今からは心が波動性を持っているのではないかと思わせた、いくつかの傍証を観て行きます。
1.量子論とユング心理学の類似性
自然界の2大理論として、「相対性理論」と「量子論」がありますが、相対性理論は時間や空間という「自然界の舞台」としての理論、量子論はその舞台に立つ電子などの「自然界の役者」としての理論と言えます。
量子論がかかわらない物理学を古典物理学といい、ニュートン物理学、電磁理論、相対性理論が含まれます。
古典物理学はラプラスの魔物に代表されるように「因果論的決定論」ですが、量子論(実証論の)は、非決定論であり、ニュートンの「モノの世界観」を「コトの世界観」に変えたといえます。量子論は従来の概念からは素直に了解しがたい概念を含むものですが、つまるところ量子論のキーワードは前述のように、2つに要約されます。
① ミクロの世界では光や電子など量子的物質は、「粒子の性質」と「波の性質」を持っている。(波と粒子の二面性)
② ミクロの世界では一つのものが同時に複数の場所に存在できる。(状態の共存性)状態とは、位置やスピンのことを言います。
これらの、相反する性質が相補って存在し機能することを、量子論の中で、ボーアは「相補性」と言う概念で説明しています。
また量子論では、量子同士が<超>光速信号で繋がっていることを思わせる非局所性(因果律では説明できない)は避けがたいものとなり、瞬間移動の存在(量子テレポーション)を立証しました。
、
ユング心理学は、意識、無意識の間や、4つの心理機能の間に相補性があり、心のバランスを保っていることを強調しているし、また心の働きに、意味のある偶然の一致meaningful coincidenceや共時性synchronasity の概念でテレポーション(遠隔作用、瞬間移動、虫の知らせ)の実在性を言っています。
これら相補性と、共時性、共存性の概念における量子論とユング心理学の類似性から、心の作用と量子の振る舞いには共通性があり、したがって量子の持つ性質が心にも共通するものとの推測が成り立ちます。
2.心の量子論;ペンローズの考え
ホーキングと共に「特異点定理」を証明した世紀の天才数理物理学者とされるロジャーペンローズは心の仕組みを、意識は必ず物質的な基礎を持つという還元的唯物論の立場から、意識を量子論を基礎に、それを越える量子重力理論で解明しようとし、それをツイスター理論で説明しています。彼は量子論ではアインシュタインの実在論のグループに属しています。
ペンローズの言う意識は、意味の理解から生ずる非計算的なものであり、ロボットのように計算的なシステムで動くものは、意味の理解ができないから意識が生ずることはないといいます。
また、生存のためには意識は機能的な役割を果たすと考えている。
意識は部分の寄せ集めではなく、一種の大局的な機能的な能力であり、おかれている全体的な状況を瞬時に考慮し判断できることから、量子力学が関係すると考えています。
また、そもそも現在の量子力学はマクロの説明は全くできないことから根本的な欠陥があるのではないかとの考えから、量子力学を越えた「万物の理論」としての量子重力論の必要性を主張し、それをツイスター理論で説明しようとしています。
そして、意識の作用は量子重力的な効果、すなわち波動関数の自己収縮(客観的な波動関数の収縮)で説明できるとしています。
具体的にはニューロンのマイクロチューブルで、量子学的な重ね合わせが形成され、コヒーレント状態(干渉可能な状態]が保たれると意識が生まれ、量子重力理論で与えられるエネルギーの閾値に達すると波動関数の自己収縮が連続して起き、意識の流れが生まれるとしている。
⇒マイクロチューブリンのコヒーレントに重ね合わされた量子力学的な状態は、まさしく波動を示すものであり、波動関数の自己収縮が自己組織化されオーケストラのように調整され、意識に関連しているという意見は、少なくとも意識に波動的性質があるということ意味しているといえ理と考えます。
3.ニューロンは波動である。
心脳問題で述べたように、現在では、心はニューロンの何らかの働きによって生まれるというのが、多くの見解の一致するところであります。
またニューロンは細胞であり物質であるから波動性(物質波)があることになります。そのニューロンから生まれる心に波動性があるとするのは、うしっろ自然な解釈ではないかと考えます。
4.神経活動の同期と意識の結合問題
意識の第二のレベルである気づき(視覚、聴覚、嗅覚などの感覚)は、脳の異なる複数の部位で処理された情報を一つに統合、結合して認識する必要があります。その機序は神経活動が同期した時に情報が束ねられて意識が生じるという理論があり、実験的にも視覚系(Singer)や嗅覚系(Freeman)において確認されています。⇒これは意識が同期によって生じるとしていることを意味し、すなわち意識が波動であることを示しています。
5.単細胞の振動の意味すること
粘菌はアメーバ様運動をする巨大な単細胞ですが、高等動物の脳の働きに類似する高度な情報活動を行っているとされます。この秘密は、リズム性と形状変化にあります。
原形質は振動する代謝反応に起因するリズムを示し、したがって細胞は多数の振動子が結合したネットワークを形成します。
形状変化は振動子間の結合状態を変えます。
このように粘菌は、脳でのシナプス結合の変化に相当することを時々刻々と行い、細胞全体にわたる動的パターン形成をもとにして情報判断や行動制御を行っているといいます。(上田哲男、中垣俊之:細胞に心はあるか。脳と心のバイオフィジックス、共立出版社、1997年)
⇒これは細胞心理学の可能性を展望する論文の要約ですが、原生生物においても、意識が振動に関連する可能性を示し、また、細胞の振動子が結合し全体系の集団ダイナミクスが情報処理や計算の基礎になっていることの示唆は、現在、脳の活動が神経回路網のダイナミクス(ニューロンシナプスの可塑性の問題)として理解されつつあることと関連していて興味深いものです。
6.身体における同期現象に心が影響する
心拍の力強い、超多数回の運動は、心筋細胞一つのリズムが、同期して細胞塊の集団リズムに変わり、大きな心拍動になることで実現している。
これは自然界に見られるミクロリズムを集めマクロリズムにまとめあげようとする自然界の力です。
リズム振動は波動であり、心拍のリズム振動は神経系、内分泌系、免疫系の伝達物質の影響を受けますが、心の影響も受けます。心も波動で心拍リズムに同期するためと考えることは出来ます。
7.中村雄二郎の汎リズム論
哲学者中村雄二郎は、自然、宇宙のあらゆる物理現象から生命現象はリズム振動が基礎であり、音楽の感動も、リズム体である音楽が、同じくリズム体である生命体に共振作用によって身体に働きかけるためであり、単に知的、精神的なものではないと述べています。広く絵画などの芸術に対する感動も、根源はリズム振動の共振であるという「汎リズム論」を言っており、心、意識は波動であるとの考えであります。[中村雄二郎:表現する生命、青土社、1993、中村雄二郎:共振する世界、青土社、1993)
⇒ここでは、身体、精神が振動体であることを前提においています。
8.精神症状と量子論の親和性
幾つかの精神症状は量子論の現象に類似性があり、意識が量子論で表現されている現象なのかもしれません。
-
① 自我漏洩とトンネル効果
電磁波は障害物を透過する性質があり、可視光はガラスを透過するし、携帯の電波も壁を透します。量子も波の性質があるため、あらゆる物質は、理論的には壁をすり抜けることが出来ることになります。
原子核は通常、「強い核力」により陽子、中性子が強固に繋がり、また周辺をエネルギーの障壁で守られているので崩壊することはありませんが、原子核のアルファ崩壊はアルファ粒子がトンネル効果でエネルギーの壁をすり抜けることで起きるとされています。
エネルギーと時間の不確定性関係では、ごく短時間であれば、障壁を越えるだけの大きなエネルギーを得ることが出来るため、ボールが障壁をすり抜けたように見えるわけです。
自我は原子核に例えることが出来る過と思います。自我は自我境界で守られ統一性が保たれていますが、しかし、自我も境界が脆弱化すると、自我が漏洩し、作為体験、考想吹入、考想奪取などの症状を呈します。(幻覚、妄想も関係する?)
電磁波、量子の波動性がトンネル効果をもたらすように、自我漏洩もトンネル効果の一種と見れば、心に波動的な性質があると捉えることは出来るのではないでしょうか。
-
② 多重人格と多重世界解釈
ICD-10では多重人格障害、DSMⅣでは解離性同一性障害と呼ばれる、「2つ以上の別個の人格が同一個体に存在し、ある時点ではその一つだけが明らかになる病態」がありますが、これは量子論の、コペンハーゲン解釈の「多様性が一つに収縮し、他は瞬時に消滅する」という矛盾を、「多様性の数だけ多世界が存在するが、そのうちの一つだけを認識する」と解釈することで、矛盾を解消する多世界解釈に通じるものであるようにも思えます。多世界解釈では、多世界の各々に自我は存在し得ますが、複数の世界に行き来することは出来ず、一つの世界を認識すれば他の世界を認識することは出来ないとされます。多重人格は、なぜか複数の世界を行き来しますが、多世界という状態は奇妙な一致があります。
-
③ 「力動」、「相補性」と「量子的なからみあい」
フロイトは無意識と言う概念を作り、それは常に意識と相互に密接に関係性を持っているとし、ユングも内向、外交的態度や主機能、劣等機能の関係において、意識の態度が一面的になると、それを相補う働きが無意識内に存在することを強調しています。
量子論においては、量子はある関係性においてはペアになることがあるとされ、その関係は空間的に距離が離れても無関係にはなれないとされています。
例えば「シングレット」という特殊なペアの場合、量子1と量子2のどちらかが「上向き」の回転軸を持っていると、もう片方は、必ず「下向き」の回転軸を持っていますが、観測する前は、量子1も量子2も具体的な回転軸の状態は決まっておらず、決まっているのは「互いの回転軸の方向が反対だ」ということだけである、というような関係を、量子1と2は「量子的なからみあい」の状態にあるといいます。
このからみあいの関係は、意識無意識の力動関係、相補性に通じるところがあります。
9.DSM5の見解から
DSMⅤでは、DSMⅢ,Ⅳの診断可能な症状の項目を集めたカテゴリ―診断学的な考えを改め、統合失調症、広汎性発達障害カテゴリーには、類似周辺疾患として独立した障害名が外され、統合失調症スぺクトラム、自閉症スぺクトラムとして、一つのスぺクトラム(連続体)として、扱うようになりました。スぺクトラムとはもともと「混ざり合ったものを分けて並べたもの」と言う意味であり、いくつかの波長の電磁波が集合(干渉)していた光をプリズムで屈折させ分散させると、明確な境界が無い連続性のある波長帯を描くということが、光が波動であることを示す現象をいうことから、スぺクトラムと解釈できる精神症状も波動的性質を持つとの意味合いを含んでいることになります。
DSMは、現段階では精神障害のすべてが一つのスぺクトラムであるとはされていないが、単一精神病の概念の方向性に向かっているように見受けられます。
これは心が波動であるという仮説、解釈の傍証になるものと考えています。
以上羅列した各事項は、各々が、心、意識、精神に波動的な性質があることを含んでいたり、示唆するものであり、それらが集まって全体性として全く別の新しい意味あいとしての波動性を生じた、ものとは言えません。従って、「心が波動である」という考えは創発には当たらず、単なる解釈といえるのかもしれませんが、「精神波」というような心の状態を示す包括的な言葉が無かったことから、そのような表現を考えたものです。
新しい心の捉え方―霊性と心
話は少し戻ります。
私は形成外科医時代、自分の外観に悩み、心を閉ざしてしまった子供達をたくさん見てきました。そうした子どもたちは、「自分は生きている価値がない」「自分は生きていてはいけない」とさえ、思う子もいました。
これは手術が成功して、外観が大分良くなっても変わらないこともありました。手術を行った医者として、そうした姿を見るのは本当にやりきれないものがありました。
そこまで心を病んでしまうと、今度は手首を切るなどの自傷行為が始まったりします。そうした姿を見ていて、私は彼らに共通して、「自分を愛することが出来ない」「生きる強さが足りない」ように感じていました。
その後、精神科に移り、患者と関わりながら、「人の心とは何だろう?」と考えていた頃、ある言葉が気になり始めました。
それは霊性という言葉です。霊性とは英語でスピリチュアリティのことですが、この言葉は昨今、メディアなどの様々な場面で取り上げられますが、殆どが、透視、予知、バイロケーションなど心霊現象に関するもので、精神との関係で語られることはありませんでした。
本来、霊性とはその人の精神的傾向や崇高さを示す言葉だと私は考えています。「心の正体を見つけよう」と模索していた私は、霊性という言葉に出会って、「人には霊性というものがあるらしい。もしかしたら、それが心と関係しているのではないか」と思い始めたのです。
形成外科医時代の患者であった子どもたちに、生きる強さを感じられなかったのはこの霊性が弱いか、もしくは、霊性が自分の中でうまく育っていなかったからではないか。育ってきた過程で本来持っていたはずの霊性が薄らいでしまったり、もしくは、うまく機能しなくなったのではないかと考えました。「生きたい」と思うことは生命の根元的な部分なのに、本人の意思とは関係なく、そうした生命の根元的な部分を強く持てないでいるのかもしれないと感じました。
霊性とはつかみどころのない概念です。私も自分なりに考えましたが、出てきた結論は、「霊性とは、真実と呼ばれるものや道徳的に良いとされていること、美しさへの憧れなどの、いわゆる、『真善美』(ルビ:しんぜんび)につながり、また「自尊心」や「良心」、「憐れみ」など、自我を形成するメカニズムとは別の、それを超越したものではないか?
さらに言えば、「人が生きる意味、価値」という、人がアプリオリに持っているものにつながるのではないか、というものでした。
生きる意味の捉え方が変わると、生き方そのものも変わっていきます。
それはアドラーが「ライフスタイル」としてコフートが「組織化原則」として述べていることに通じるものでもあります。
心について、また「精神と物質」、「生命、自然と宇宙」について考える時にも、同時に霊性について考えることは、人にとって非常に大きな問題ではないかと思い始めました。
国際的にも注目されている霊性という概念
私がそう思い始めたのは、1998年、人類の健康促進のための国際機関WHO(世界保健機関)が健康の定義に「霊性」を入れようとしたことがあったことにも関係します。
それ以前のWHOの定義は、「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいう」というものでした。
さらにそこに、「人間としての尊厳や生活の質を考えるために必要な霊的な健康がある」を加えようとしたのです。その案は議会で可決されましたが、「それまでの定義だけでも十分に機能している」という理由から、定義の変更には至らなかったそうです。
しかし、定義に入れようとするくらいですから、「霊性というものがあり、人の健康に影響を与えている」という認識が国際的にあるのだと感じました。
私はそこで、「世の中には説明のつかない法則がある。その法則は、人の心の揺るぎなさを含め、自然の摂理と絶対的なつながりがあるのではないか。それがつまり、霊性と関係があるのではないか」と思ったのです。そうした見解に至ったのは、精神科に転科して2年目頃で、心を知るために量子論を勉強している最中で、量子論が示した森羅万象の曖昧さ不確実性に対する素朴な疑問からです。
心理学、哲学と同じように、精神医学も、これまで霊性という領域を扱おうとしませんでした。この霊性の領域を精神の全体像に含めて考えないと、心というものの説明は十分につかず、精神障害の解決方法も見えてこないような気がしたのです。
霊性と心の状態をあわせて考えた時、初めて心と体の関係も全部説明つくのではないか。そして、霊性は、単に心の上位にあるだけではなく、生命、社会、自然、宇宙に至る万物万象を統合する超越した力、摂理と関係しているのではないか、と捉えると、心の状態やその他の問題も説明できるのではないかと考えたのです。