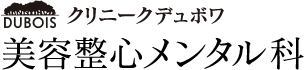人生のライフサイクルで考える「思秋期」について
人は年代による心身の発達ぐあいや社会性を含めた人生の役割によって、一生を区分して考えるライフサイクルの概念が昔からある。近代の精神医学では、フロイトが精神の発達を性的衝動の発展として捉えて壮年までを6期に分けて説明し、ユングは自己実現の概念から人生の後半にも意義を見出し、エリクソンは両者の説明を取り入れながらも、生まれてから老年期までの一生を8期に分けるライフサイクル説をのべている。また、日本の精神科医である神谷美恵子は壮年期と老年期の間の55~65歳位を「向老期」としている。
一般的には、「初老期」や「中老期」と言われたりするのだが、中嶋は、生き方を立て直す時期として「思秋期」とするのが理解しやすいのではないかと考えている。
思秋期症候群とは
思秋期は思春期に相対する言葉である。向老期に変わる言葉として思秋期を提唱する理由は、思春期が家族的共同体から社会的共同体に参入していくに当り必要なアイデンディティ(自分であること、自分固有の生き方や価値観)を形成するのに対し、思秋期は社会共同体から離脱するに当って再び新しいアイデンディティを確立し直す必要がある時期となり、対称的に位置づけられると考えるからである。
思秋期は「老い」というものを嫌でもはっきりと自覚しながら生きて行く始まりの時である。人間の心理は「老いとか死」をあえて自覚しないようにし、自分には無関係なものとして否認しつつ生きている。そのため、老いを突然意識させられることは、当人にとっては一種の驚きであり、場合によっては暴力的とも思える体験となるのである。
この年代の心理を「抵抗」と表現する小説や論説も多いが、どんなに抵抗しても否応なしに自覚せざるを得ないのは、まず身体的な衰えであり、認知機能の衰えである。
また、心理的には定年退職など仕事からの撤退を意識せざるをえないことが大きな心の重荷やストレスになる。定年・隠退は、それに伴う経済的な問題もさることながら、心理的には「無用者になる」と疎外感や喪失感を強く感じさせる。
この頃は子どもたちも独立し、家庭でも自分の役割・存在感が希薄になり、公私ともに必要とされていない、無用者になったという意識が、それまで自分を支えてきたアイデンディティを大きく瓦解させてしまうのである。
それに加え、兄弟・友人の死別が始まり喪失体験が重なる。特に配偶者の死別は大きなダメージを与え、癒しがたい孤独感を残す。やがて来る人生の終結に向かって、自分の人生を振りかえり始めると、「果たして自分の人生はこれでよかったのだろうか?」「このまま朽ち果てて良いのか?やり残したことはないのか?」などと思い、いざやり直そうと思っても自己実現をはかるには時間的にも経済的にも不可能なことが多く、無力感や絶望感が湧いてくるのである。
思秋期は思春期と並んで人生の危機を感じる時期なのである。しかしその決定的な違いは、思春期が守られていた巢からの旅立の不安であるのに対し、思秋期は終末への旅立に対する憂いであるからだ。いずれにしても、この先の自分のあり方を決めなければ生きていくことが出来ないところに危機的な状況がある。
この時期は心身の失調が起こりやすくなる。喪失感、疎外感、無力感、絶望感から精神は不安定な状態になり精神失調も来たしやすい。実際、この時期に抑うつ・焦燥感から初老期うつ病になることも多い。こころのバランスが崩れると、それに相関して身体のバランスも崩れ、身体的な病気にもかかりやすくなる。成人病や免疫力の衰えから来るガンに罹患しやすくなるのもこの頃である。また頭痛・肩こり・不眠など自律神経失調症状や様々な不定愁訴を訴えることも少なくない。中嶋では、これらを総じて思秋期症候群と呼んでいる。
治療・対処の方法
思秋期症候群とは、まぎれもなく壮年期から老年期に至る加齢現象に伴う全体的な症候である。秋の不安定な季節にも似て、心身の恒常性が不安定になり、自律統合性が揺らいでいることが原因と解釈する。加齢・老化とは、「あらゆる心身の機能の低下とホメオスターシス(恒常性)の減退」と定義され、また「エントロピーの増大による生理的な全体的な機能の衰退」ともいえる。
しかし、加齢・老化は止めることはできなくとも、エントロピーの増大を極小化させることでスピードを抑えることはできる。思秋期症候群に対しては心身の恒常性の揺らぎを立て直し、加齢を抑制することが必要で、そのためにはホメオスターシス機能を強めるために、自律統合性機能の揺らぎを立て直すことが基本的な対策になる。
自律統合性機能は心身相関のバランスをとり、心身の恒常性を維持する機能であるため、心的恒常性にはマインドフルネスレジリエンス療法(MBRT)を、身体的恒常性にはレジリエント生活・食事療法を取り入れるのが有効になると考えている