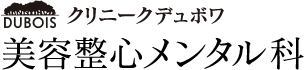エリクソンのライフサイクル論②
2017年04月17日
これまでに述べてきたように、人間の発達論は、フロイトの心理・性的発達論がかつての中心的なアイディアであり、精神の発達を性的衝動の発展として捉えるものであったが、エリクソンは家族の人間関係を重視し、社会的、対人的な側面から発達を見直そうとし、人間は「身体、心理、社会的な存在」として捉えた。そして人間は、確かに3歳くらいまでの精神発達が、性格を決め、人生後半におきる様々な問題も、元を正せばこの幼児期の葛藤に還元される要素が高いことは認めるが、それだけではなく、生涯の各年齢に要求される社会的な課題が解決されず精神的問題が発生する場合も少なくない、とした。
生涯全体を変化して行く主体の発達として捉えて行こうとしたのがエリクソンのライフサイクル論であり、生涯を8つの発達段階に分け、そのおのおのに必要な心理社会的な能力、自我の力を心理力動的な観点から捉えている。各段階の課題と、その対立的な課題を提示し、生きて行くためには、心の中で両者のバランスが必要であり、バランスを崩すと危機的状況に至り、その後の発達に影響し障害を来すので、順番に漸成して行く必要があるとし、ライフサイクルの概念を報告した。
前回では第一期の乳児期に基本的信頼が獲得されるのが非常に大切であることを述べた。今回はⅡ期からⅣ期までを述べる。
Ⅱ.幼児期(2~4歳)「自律性(/恥、疑惑)」を身につける―愛されながら自信をはぐくむ
2歳から4歳ころに乗り越えなければならない危機的な主題は「自律性」の獲得である。
自分を律すること、自らをコントロールすることである。
例えば、躾というような、外からの圧力を受け入れ、自分の衝動を統制し自分のなかで折り合いをつけ、どう振る舞うか決めて行く枠組みを作ることが、自律性を築く中心的な仕事になる。
自律性とは、外からの要求と自分の内からの要求とがバランスと取ることであるが、うまくいかないと、「うまくやれていない」という、外からの要求に応えられない恥の意識が生まれ、また「自分はいったいどうなっているのか?」と言った自分に対する疑惑を持つようになり、生きて行くことが苦痛になってくる。
自律性は、乳児期に自信が育っていないと獲得できない。そして自信は、乳児期に基本的信頼が獲得できていないと生まれないのである。基本的信頼は母親への愛着が必須で、母を信じ依存することで信頼感、安心感を得ることなしに、自分を信じ、人を信じるようにはなれないので、自律性は基本的信頼の延長上にあることになる。
つまり、自信のない子にセルフコントロールを教えること、つまり自律性を身に着けさせることは極めて困難なことになるのである。
幼児期は、「ボク スル」の一言から始まる。すべてを母親に頼り、親まかせにしていたものが、自分でやろうとする。母親の言う通りにしなくなる。ぐずったり、駄々をこねたり、口答えをしたり、憎まれ口をたたいたりする。
これが、第一反抗期と呼ばれるものであり、3つ4つの憎まれ口は自律の為の行動化(acting out)とみられる。この時期の子供の行動は、母親をイライラさせたり、不安にさせたりするが、母親が行動化に伴う危険を見守り、母親自身の不安を乗り越えて育児に当ることが、子供の自律を達成させる鍵になる。この第一反抗期を示さず自律を済ませないと思春期の自立(親や世間や今までの自分自身への反抗である「第二反抗期」を通して自己を確立する)に際してアイデンディティの確立が困難となり、思春期に、不登校、家庭内暴力、リストカット、摂食障害等の問題行動を招くことになる。第一反抗期を思春期の第二反抗期に持越し一度にやらなければならないために問題が大きくなるのである。
自律しようとすると、自分の判断が必要となる。親の判断と異なる判断をしなければならない。最初は判断というより、「母親はこうしろと言ったが、自分はこちらの方が面白そうだ」という衝動である。
フロイトは衝動を抑える働きとして「超自我」の概念を仮定し、超自我は幼児期に形成され始めるとしている。超自我は社会的良心であり、社会的秩序であるが、まず家庭内の秩序をモデルとして生まれてくる。家庭内に秩序が無かったり、家庭内のモデルが社会の秩序と大きく食い違っていると子供の超自我は混乱を起こし、超自我形成が不全を起こす。
子供の超自我モデルの最初は父親であり、子供は母親をとおしての父親イメージ像を作る。ので、母親が、父親イメージは、「尊敬と畏怖」「寛容と厳格」の両方が必要だが、この二律背反的なものをバランスをとって母親が伝えることで、子供は自分の衝動の統御と解放のバランスを学ぶことが出来る。
従って父親の不在は、超自我形成におおきなひずみを残すことになる。
また母親の不在は「母なるもの」の形成に大きな影響を与える場合が多い。
具体例を見ると、幼稚園では、協調出来ていい子であるが、家では駄々っ子で手のかかる子供が、基本的信頼を獲得し自律性を持っている子供に相当する。幼稚園でルールを守れない子は、自律性が得られていないのであり、それは、その前の段階で基本的信頼を感じる相手が持てなかったこと意味し、従って躾をするのは簡単なことではない。
躾とは子供に大人の文化を教えて行くことであり、言葉が理解できるようになる頃に、例えば、手ではなくスプーンで食べよう、おしっこはトイレでしようなどと教え、何をするか、しないかは、子供が考え、選べるようにするのが躾であり、自律性です。教えたら待つことで自律性は育っていきます。
また、
サリヴァンによれば、人間は人との関係によって人間になる。他者があるから自己がある。他者の存在をしっかり実感し、他者を認めることが、その後の社会的人格を形成する基盤になると言い、自律とは他者と調和がとれることを意味 し、そうすることで、対人関係を作ることが出来るようになる、としています。
サリヴァンは精神医学を人間関係の学問とし、心の病気の治療は人間関係が重要であるとしている。
色んな研究によれば、いじめっ子は、親子関係に問題がある子に多いという結果が出ている。母親を信じることが出来、依存出来、親子で喜びや悲しみを共有できるコミュニケーションが取れれば、いじめっ子になる確率は低いとされる。
また将来、不登校、家庭内暴力、リストカットなど問題行動、適応障害などの症状は、乳幼時期に基本的信頼と共感性と自律性が獲得できていない場合になる可能性が高いとされている。
Ⅲ.児童期(4歳から7歳)「自主性(/罪悪感)」を育む―遊びのなかで挫折と成長を経験する
4歳から7歳ころ児童期のテーマは「自主性」「自発性」です。
「自発性」とは、自分の衝動のままに行動することではなく、外的・内的な力が統合できる能力(すなわち自律性)がついてから、自分の欲求を表現できるようになることを自発性という。
すなわち外的・内的なバランスを保ちつつ、行動出来ている状態、自分が行動の中心になることを意味し、このような心の状態を「自主性」ともいう。
自主性がうまく獲得されないと、行動が規範を冒し、はみ出た行動になり、「悪かった」「失敗した」「規範を冒した」という罪の意識(罪悪感)になるとしている。
「自発性、自主性」は、好奇心を持って自分から活動することで、積極性、主体性、目的性という側面も合わせ持っている。
このように、この時期に、自分が心の中心あるという意識を持つことが,アイデンディティを形成する上での心の基礎になるとされている。
エリクソンは児童期を遊戯期とも言い、探求心、実験的に活動する力、創造力、空想力,想像力は皆遊びのなかで育つとし、この時期に最も大事なことは「遊び」だとしている。
児童期の子供は、昨日出来なかったことを今日は出来るかな、と遊びのなかで実験的な発想を繰り返し目標に達成していき、限界を伸ばそう、広げようとし始める。
ピアジェは「この時期に遊んでおかないと、将来優れた想像力のある仕事は出来にくい」としている。
この時期に遊んだ子は、将来努力することが出来るようになる。
遊びのなかで壁にぶち当たり、それを乗り越える工夫をして可能性を広げた体験は、目標を設定し、努力出来る自主性、積極性、主体性に繋がっていくからである。
この時期にうまく遊べなかった子は、ニートになる傾向が強い。
「遊ぶのが仕事」というのは本当であるが、遊びが豊かに発展するのは次の学童期(小学校時代)であるが、このころから慣れ準備をしておくことが必要なのである。
Ⅳ.学童期(7歳ヵら12歳)「勤勉性(/劣等感)」の基礎づくり―授業時間より休み時間に多くを学ぶ
小学生時代のテーマは勤勉性です。
子供は、内的な知的要求と外的な要求とがバランスがとれていれば、子供は学ぶことが興味深く面白いから、喜んで学校の勉学をせっせとする。毎日の勉強のなかで新しい発見をする喜びを体験出来たら、心の中に「自分は自分なりにやっていける力がある。学ぶことは面白い。」という感覚、有能感が育ってくる。有能感は社会的に生きて行くうえで欠かせない心の力である。有能感が勤勉性に繋がり、劣等感が勤勉性を損なう。
外的な要求が強く、有能感が育たないと劣等感が生まれてくる。(実はこの有能感は友達との付き合い遊びのなかで育つ。みんなとやっていける、ついていけるという自信が有能感になるのである)。
小学生の過ごし方が大人になった時、社会的に勤勉に生きていけるかどうかの重要なポイントになる。その基礎づくりになる。
勤勉に生きて行く元を、この期間に身につける。
社会に対する自分の適格性を確認する時期でもある。
同世代の仲間と、道具や知識、体験を共有することで勤勉性を獲得していく、将来の社会的な活動の予行演習を始める、基礎作りをする。
友達は質より量で、たくさんのことを教え学ぶことに意味があるとエリクソンは言う。勤勉性は勉強ではなく遊びの人間関係で育つ。授業の落ちこぼれは社会人としての落ちこぼれに直結しないが、休み時間の落ちこぼれは社会人としての落ちこぼれに直結する。休み時間に友達となかよく、生き生きと過ごせるかが重要。大人からではなく、友達に教えられ、教える経験が社会的に勤勉に生きる基になる。
遊ぶことは意識はしないが、よく遊んだ子は、将来よく働く
対立課題は劣等感。
この学童期に勤勉性を学ばないと、社会に出てから勤勉に働くことが出来ない。会社や社会が自分に期待していることを理解して、その為に習慣的に努力することが出来ない。なぜなら、職場で同僚、先輩、上司と自然な交わりが出来ないから。「会社が合わない」のではなく、「会社で健全な人間関係が出来ない」豊かな交わりが無い、学び合うことが出来ないので、自分の知っている事しか出来なくなる。
適応障害は、学童期の本当の意味での学び合う経験を積んでいないか、それ以前の自律性、基本的信頼性が得られていないためのつまずきが表出したもの。友達と遊びながらコミュニケーションをした経験が大事。
小学校で勤勉性を獲得できなかった子は社会の中でコミュニケーションが、人間関係の構築が出来ない若者になる。会社のせいにしてはやめることを続ける。
働き続けることのできない若者は、意欲や知識技能の問題ではなく学童期、あるいはそれ以前のつまずきがある。
小学校高学年から中学校前半頃(10歳から14歳頃)をエリクソンの思春・青年期から前思春期として区分する考えがある。
なぜなら、この時期特有の精神病理があり、それが将来に大きな影響を与えるからである。
サリヴァンは、この年代の友達関係の人格発達に対する重要性を強調している。
前思春期になると、子供の心の中に愛の能力ないし親密さを求める気持ちが芽生え、同性の親友が出来、二人の間で、人生や世界におけるあらゆることに自分たちの感覚、思考、感情などの体験について相互に語り合い確かめ合うようになる。そして他者の視点を取り入れることで自己中心的な視野を超えて自他共通の人間性に目覚め、人間一般や共同体としての社会や世界に対する共感的態度が持てるようになる。
前思春期が重要なのは、この時期が友達関係を通じて共感性が増大する時期であり、それがその後の人格の統合的発達の基盤となることであり、同性、同世代の友達関係を十分経験していないと、思春期に入ってから様々な問題が生じるからである。
思春期とは、性機能の発現に伴って性欲を体験し、自己が性的な存在として意識されるとともに、異性が異性として登場し、性欲という身体の次元の欲求と親密さという精神の次元の欲求絵を統合的に充足させることが、一つの課題になってくる時期であるからである。
前思春期は友達関係を通じて共感性が増大する時期であり、それがその後の人格の統合的発達の基盤となる子rとをとりわけ強調したいからである。
学童期のつまずきは社会的に勤勉に働くことが出来ないという形で現れる。会社や社会が自分に期待していることを理解し、その為に習慣的に努力することが出来ない。その理由は、職場で同僚や先輩、上司と自然な交わりが出来ないから。会社が合わないのではなく、会社で健全な人間関係が築けないから。豊かな交わりが無い、コミュニケーションが取れないから学び合うことが出来ず、自分の知っている事しか出来なく、孤立してしまうのではないか。
仕事の努力をするだけでなく、人間関係の作り直しが必要。
働き続けることのできない、適応障害の若者には、本人の意欲や、技能の問題だけではあなく、学童期あるいはそれ以前のつまずきがある。コミュニケ―ション、人間関係のやり直しが必要
Ⅴ.思春期・青年期(13~22歳)「自己同一性(/同一性の混乱、拡散)」-仲間を鏡にして自分を見出す。