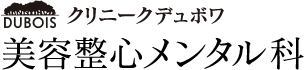不登校―その意味と変遷
不登校という言葉は、よく知られている割には、比較的新しい言葉で、ウィキペディアでは
「不登校とは、学校に登校していない状態のことである。登校拒否とも称される。日本における「不登校」の語については、研究者、専門家、教育関係者らの間で全国的に統一した定義が無く、極めて多義的である。」としている。
多義的とは、すなわち、てんでんバラバラに使われているあいまいで不明確な言葉という意味である。
しかし、実際にはこの言葉の起源も、本来の定義も明確であったのである。
1968年日本児童精神医学会で思春期精神医学のシンポジウムで精神医学者清水将之が使ったのが始まりで、その時きちんと定義づけがされている。
「さて、子供が学校に行かないという現象は、どのよなことを意味するものであろうか?諸疾患のための就学不能、親の無理解や貧困による不就学、非行などが原因となっている怠学などを除外したものを一括して不登校(non-attendanncde at school)と称する。」とした。
がしかし、その後言葉は一人歩きして「きわめて多義的」なものに拡散してしまった。
ここで言う除外する3つの理由の一番目の病気で休むのはやむをえないし、生活が苦しくて、学費の負担に耐えられなかったり、親の都合で学校を休ませるというのも理解できる。非行でさぼるというのも了解可能であり、これらの理由による欠席は学校教育が始まった時からずっとみられたものであり、それなりに説明のつくものであった。
ところが、そこにそれ以外の理由による学校に行かない現象が起きたため、それに対して新しい呼び名が必要になったということなのである。
1960年代の初めに、「病気でもなく,利発でまじめで礼儀正しく、身なりも上品で、家庭環境も良く、学校でいじめとか人間関係でいやなことがある訳でもなく、勉強も好きで、成績もよく、本人も学校は楽しく好きで行きたいと言っているのに、でも朝になるとなぜかどうしても行けない」という子供たちが現れてきたのである。上記のような、従来の経験や考え方では説明がつかず、理解困難な「欠席」の形が出現すると精神医学に答えを求められ、そこで精神医学から「不登校」という呼び名がつけられ、上記のように定義がされたのである。ここでは、病気が原因であるものは除外されるので、不登校は本来的には病気ではないことになるが、本人や周りがそれに悩み葛藤が生じ生活に支障が出るので、不登校は病気ではないかもしれないが、児童精神医学の中心的なテーマになっていったのである。
文部省は、理由の如何を問わず、継続的であれ、断続的であれ年間50日以上学校を欠席するものを長期欠席」と定義していたが、1991年に週休2日制になると年間30日以上に変更した。
そうして、何であれ長期に学校を休んでいる状態を「長期欠席」と呼ぶことになったのだが、その中で、本人自身であれ、周りのものであれ、そこに悩みや不安、葛藤が生じているものを「不登校」とするのが良いのではないかとする考えが出てきた。なぜなら、不登校とはもともと精神医学から生まれた臨床の概念であり、臨床とは、ある事態が何らかのケアを要するケースとみられたときに、それにかなうケアを行う行為を言うので、「長期欠席」でも、どこにも悩みも不安も葛藤ももたらさず、万事うまくいっていれば、ことさら「不登校」と名付けて医学化する必要がないからである。
ただその長期欠席が明らかな病気からもたらされているものは、不登校とは言わないことになっている。「肺炎で学校を休んだ、長期欠席した」と言っても「肺炎で不登校した」とは言わないのは、これは清水の最初に定義したものと同じで矛盾しない。微妙なのは心理・社会的な失調の時で,「対人恐怖症で不登校になっている」「不安障害による不登校」とは言えることだ。その違いはどこにあるか?
肺炎など身体的な病気では、欠席はその病気の症状ではなく、それが原因で休んだということであるが、対人恐怖症や不安障害による欠席は、欠席自体を症状の一つと見なすことが出来るのである。
この違いから明らかなことは、学校教育という営みから全く離れた別の要因から生じた欠席は「不登校」とは呼ばないということで、最初の定義で外された貧困による欠席も教育とは直接関係が無い経済問題だからである。
では最初の除外要素の「怠学」はどうかというと、これは自分の意志で確信犯的にさぼることで、悩みや葛藤が生じていないので不登校にはなじまないことになる。
従って「不登校」を除外診断ではなく、直接的に定義すると、「学校教育という営みに孕まれる何らかの要素との関連において長期欠席が生じ、そこに悩みや不安、葛藤が生まれているもの」となる。(滝川一廣)
不登校は、学校教育という営みに孕まれる何らかの要素との関連という意味合いで、教育問題ともいえるし、同時に「悩みや不安、葛藤が生まれている」という側面からは医学的な臨床問題ともみなされる。不登校研究の長い歴史の中では、この欠席現象を教育問題とみるか臨床問題とみるかで、意見対立が起きてきたが、どちらの問題でもあるというのが正しい理解であると思われる。
上で述べた、不思議な新型の長期欠席は「不登校」として抽出されたが、このような不思議な欠席現象は、一足早く欧米で見出され、1941年に、米国の研究者ジョンソンによって「学校恐怖症school fhobia」と名づけら報告された。恐怖症とは、特定の事物や状況に対して合理性を欠いた極端な恐怖心に囚われる心理現象を言い、不登校の子供たちが校門の前で立ちすくんでしまい、パニックになり動けない状況から、学校への合理性を欠いた極端な恐怖反応とみて.高所恐怖症と同じく「恐怖症の一種と考えたのである。
しかしその後ジョンソンは研究を進め、養育者(親)から離れて過ごさねばならない状況への強い不安が、これらの子供たちに共通する心理背景になっていることを発見し、この不安を「分離不安」と名付けた。分離不安は、子供から見れば親への過依存、親から見れば、過保護によって生じるもので、実は恐怖症ではなく、分離不安のために登校不能になるのではないかと推察した。「学校に行けない」のではなく、「家から離れられない」という訳である。
この考えは、日本でも支持され、「学校恐怖症」は「登校拒否school refusal 」と呼ばれるようになっていったのである。
しかし拒否には自分の意志で積極的に拒むという意味合いがあり、行きたくともいけないという実体とはぴったりしないという違和感が残り、またrefusalの意味は、「立ちすくんでしまい動けない」、というものであり、語源的にも拒否は合わないことから、「登校すくみ」などの用語が登場したが、やがて「不登校」という呼び名が定着して行った。
文部省は60年代に,「病気」、「経済的理由」、「その他」等以外の理由による長期欠席を「学校嫌い」という用語を作り、それまでの長期欠席と区別するようになった。
これは、不登校に当たる教育用語であったが、1998年からは「不登校」が採用され統一された。
しかし、不登校の成因が、分離不安だけでは、(友達の家に遊びに行く時は平気で)学校に行く時だけ、何故そのような状態になるかの説明がつかなかった。そこで滝川は、学校という所には聖性があり、それに対する一種の畏れがあること、また不登校になる子供の特徴として、裕福で、知的レベルの高い家庭の繊細な神経のこどもであったことから、一般児童の粗野でラフな環境で育だった子供達の作る学校の雰囲気に対する一種のカルチャーショックとも言うべき不安があったこと、で説明しようとした。
これらの1950年代から60年代の初めに出現した小学校低学年の新型の欠席現象として始まった不登校は、第一世代と呼ばれるが、この世代が学齢を上げるにつれ、不登校も小学校高学年、中学生と年齢層が伸びて行った。
高校進学率が上がると高校生のなかにも,退学も出来ずに、「学校に行きたい。なのになぜか行けない。」という葛藤に苦しむ高校生の不登校も現れてきた。このように年齢層が上がると、さすがに「分離不安説」だけでは説明がつかないので、「自己万能感脅威説」「回避反応説」「抑うつ不安説」など諸説が主張されるようになった。
「自己万能感脅威説」では以下のように説明する。
小学校、(中学校)までは普通に学校に行けていたのに、中学校(高校)に入ると突然行けなくなるのは、それまでは何でもよく出来る子として自他ともに認めていたのが、中学(高校)に上がって、課題が難しくなると、頑張っても上手く行かない事のある現実にぶつかるようになる。一般にはこうした体験を通して次第に自分の身の丈を知って、子供から大人へと成長していく。人間には誰しも出来ないこと不得手なことはたくさんあって当然なのだが、「なんでもできること」を自己の支えにしてきた子供にとって『何でもできる』という自己のイメージが脅かされるのに耐えきれず、ついには学校に行けなくなってしまう場合がある。つまり私的自己意識と公的自己意識のギャップ
が埋められず苦しむのである。
(これは身体醜形障害(症)にも見られる、思春期における特徴的なこころのメカニズムである。)
その他諸説があるが、どれが正しいかというのではなく、不登校にはいろんなバリエ―ションがあり、どの観点から見るかという違いに過ぎないのである。しかしどの説をとっても変わらず共通することがある。それは「中産階級以上の、生活苦は無く、子育てや教育への親の関心は高く、成績も悪くなく、学習意欲もむしろ高い子供たちに特異的に見られる長期欠席である。」ということである。
これは学習意欲の低さを共通項とする「怠学」とは決定的に違うものであったが、この新しい長期欠席は、頭痛、腹痛などの身体症状から休み始めるケースが多く、病院に行っても異常がなく、仮病による「怠け休み」を疑われることも少なくなかった。
そこで、専門家(児童精神科医)たちは、登校拒否(不登校)の身体症状を仮病ではなく病気として扱う必要性が生じ、それを神経症として扱うことで解決しようとした。つまり、頭痛や腹痛は心理社会的なストレスがもたらすものとする神経症(今でいう転換性障害、身体表現性障害)のせいであり、本人や家族や学校の責任ではないと説明し、「まずは学校を休ませ、メンタルケアをはかることが大切」と説いた。この趣旨から不登校に「神経症的登校拒否」の呼称が診断書に使われたのである。こうして医師の責任で不安や罪悪感なしで学校を休めるようになると、学校の「が」でパニックになっていた子供達は落ち付きを取り戻し、家庭内で少しずつ試行錯誤の活動を始め、徐々に外の世界と接触し新しい体験に出会い、やがて登校を再開するようになった。これが当初の不登校支援と回復の典型的なコースであった。
60年代から70年代の半ばまでは不登校の年齢層が広がり、パターンも多様になったが、長期欠席率は下降しており、決して不登校が量的に増えたということではなかった。
学校を休む児童生徒の総数は減り続ける中で、登校拒否は、ごく少数だけに起きる極めて例外的な現象であったのである。
しかし1975年を底にして中学生の長欠率は反転して上昇に向かうようになる。
これまで下がり続けてきた長欠率が何故この時上昇に転じたかは、不登校の成因を考える上で重要になる。戦後、エンゲル係数も乳児死亡率も下がり続け、75年を過ぎてもなお下がり続けているから、貧困家庭の増加とか子供の健康環境が悪化したために長欠率の上昇を来たしのではないことは確かである。すなわち長欠率の上昇は不登校の増加を意味するのである。
詳しく見ると、50年代には長欠率は全国より都市部の方が低く、より急激に下がっており、これは都市部の方が経済回復や近代化が早く、経済的理由や病気による長欠率が地方に先んじて減少したと考えられる。ところが1967年頃から都市部の長欠率が全国の長欠率を上回るように逆転して行く。地方に多かった長欠率が都市部に多い現象になったということは、長欠率の原因が貧困や前近代性から、むしろ豊かさや近代性から生み出されるものへと質的に転換したということになる。これが第二世代不登校であり、この不登校は60年代の終わりに都市部で増加が始まり、それが都市部から地方へ広がり全国的な長欠率上昇となったのが70年代の後半であった。
1950年代から1970年代始めまでの不登校は、社会全体として長欠率が減っていく中で、特異な現象として現れ「登校拒否」と呼ばれた第一世代の不登校で、本人のパーソナリティと家族関係や学校状況などの環境的な要因と関係から生じた心理現象、つまり神経症的な躓きとして捉えていた。
また第一世代の不登校は、限られた特徴的な条件を持った子供におきる現象で、輪郭のハッキリした典型パターンを持っていた。すなわち「都会の豊かな文化的水準の高い家庭環境に育ち、親は教育に理解があり、知的で真面目で成績良好で勉強も学校も嫌いではなく、同級生からも好かれ学内の人間関係に問題は見つからないといった背景を持つ小学生に限定される。」ものであり、ごく少数におきる例外的な現象で不思議なこととして注目されたものであった。
やがて年齢層が広がるにつれ、パターンにヴァリエーションが出てきて、その類型に基づいて、それを説明する説もいくつも登場してきた。分離不安説から始まって、自己万能感脅威説、回避反応説、抑うつ不安説などである。しかしどのパターンにも、共通する現象があり、それらを念頭に最初に説明した清水の定義が出来た。そのような共通する特異な現象を持つ児童生徒が1975年頃から急増したとは考えられないので、パターンから外れた今までの第一世代の不登校にあてはまらない不登校が急増したと考えるのが妥当と考えられた。年齢も地域性も越えて、生活環境、文化環境を超えてあらゆる階層の児童生徒に不登校が広がった。現在では幼稚園の登園拒否に始まって、長じては会社への出社拒否すら見られる現状である。70年代後半の不登校の増加は、60年代までの典型的な不登校の山がますます高くなる形で進んだのではなく、むしろ典型的な山が崩れて裾野が広がり怠学などの山とも繋がり全体の傘が増えたような形となって増えた。そして文部省は1994年に「登校拒否はどの児童生徒にも起こりうるもの』と認めるに至った。
何故そのようになったか?
不登校の急激な増加と高年齢化が起きると、80年代に入ると不登校を社会問題として捉えるようになった。不登校は、個人と家庭の問題ではなく青年をとりまく社会的背景、その構造の変化による現代の社会の病理現象の一つの現れとして捉える必要があると認識されるようになった。
そいて不登校の多様化が起き、大きく3種類に分類された。
1)学校に行きたい気持ちはあるが、いざとなると不安になって行けないもの
2)なんらかの理由をあげて登校に関して拒否的な気持ちを持続しているもの
3)理由もなく、何となく学校に行かず、学校に関心を失って脱落してしまうもの
つまり、行きたいのに行けないもの、行きたくないから行けないもの、何となく行けないものに分けられた。
60年代の第二次産業(製造、工業、建設、電気など)による高度成長時代から1970年代後半の第三次産業(サービス、小売り、消費産業)中心の高度消費社会への移行で、一億総中流化意識で国民も豊かさが実感されると、貧しい時代の平等を求める声よりも個人意識、自由への欲求が強くなって行った。このような70年代後半からの産業構造の変化が日本人の意識の変化を招き、それが教育問題にも影響を及ぼした。
「自由」か[公共性]かという保革の対立点、学校教育の変化、受験ストレス論の台頭、学校の価値の凋落、学校の聖性の崩壊から「学校に行く意味」が問われるようになった。
80年代は、学校論議、教育論議が盛んで、その中で不登校問題も論じられるようになった。
中でも児童精神科医渡辺位の見解は波紋を呼んだのである。
「民主社会にあっては個人の尊厳と自由が保障されることが基本であり、したがって教育もまたその理念に従って行われるべきものであることは言うまでもない。それゆえ、学校教育は制度化されていても、子供にとっては個人として本質的要求に沿って成長・発達が保障される生活の場でなければならない。 しかし高度経済成長政策が推進された時代から、各分野はそれに沿って整備、統合、合理化がなされる中で、学校教育もまたそれに沿った人づくりを目指して改変が余儀なくされた。そして教科内容は知育中心に増量・高度化され、学力が偏重される結果となった。
一方、こうした学校状況にあるにも拘わらず、子供を持つ家族は社会通念化した高学歴志向の潮流に呑み込まれ、(中略)ただひたすら形式的通学・進学に執着し、受験態勢を激化させ、子供を、その一人一人の意思や意欲に拘わらず、あたかもベルトコンベアー上の工業製品のように、何の疑問も持つことなしに、上級学校に追い込んでいるのである。
以上の点から不登校という現象を見ると、自己喪失の危機にさらされる学校状況から自己を防衛するための回避行動であると言えよう、例えそれが無意識な発現であろうとも、早期に危機を感知できる直観力はむしろ高く評価するべきである。」
(渡辺位「不登校」清水将行編[青年期の精神科臨床]金剛出版。1982)
渡辺のこの見解は、従来の不登校は子供のパーソナリティ特徴から来る一種の心理的失調とみるジョンソンや佐藤の不登校理解を根本から覆すもので、当時は強いインパクトがあった。
「病んでいるのは不登校になった子どもではない。不登校を生み出した学校教育なのだ」というもので、不登校は「病気」ではないというキャンペーンの始まりになった。
この逆転の発想は、実は当時の精神医学が「反精神医学」を掲げ、精神医療改革の運動が世界的に起きていたことと無縁ではなかった。
レイン、クーパーらは、「人間とは社会的な存在で、人間のこころの働きは個人の脳やこころの中で独立して生起しているのでなく、絶えず個人をとりまく社会的な環境の中に会って、環境とのかかわりによって生起している。従って、社会環境に過大な無理や矛盾があればこころに失調が生じても不思議ではない。ところがこれまでの精神医学は、失調を生み出す社会環境に側には目を向けず、ひたすら個人側の脳やこころの問題(病理)としえ捉えて、個人に「病気」「障害」のレッテルを張ってきた。精神障害者とされる人たちは社会の孕む矛盾や負荷のしわ寄せをこうむった者で、しかも社会は彼等を「病人」「異常な存在」として差別や排除を行い二重に苦しめてきた。精神医学者は医学や科学の名を借りて、それを女要する役目をはたしてきた。」と主張した。
渡辺の説は、レインらが統合失調症で述べたことの不登校バージョンであり、受験ストレスというレベルではなく社会体制全体の問題として捉えたところにあたらしさがあった。
すなわち「高度経済成長政策が推し進められる社会では、学校は産業のための人づくりの場と化し知育偏重・学力強化に走り、子供達は登校と進学に追い立てられるようになった。学校は本来あるべき子供達が個人としての本質的な要求に沿って成長発達が保障される、社会的な共同体に入る準備のための成長の生活の場としての機能を失ったため、子供達は自己喪失の危機にさらされ、そこから身を守る反応として「不登校」が多発するようになった。だから、この社会状況、教育状況が不登校の元なのだ。」という趣旨で、子供主体の自由教育を主張し、不登校に対しては従来の「登校刺激を避ける」ものから「登校しないもの」へと推し進め、これは、その後のフリースクールの設立に道を開いていった。
以上は70年代後半から80年代に急激に増えた不登校の原因を学校側にもとめるものであったが、一方で批判の的にされた教育サイドからは、原因を家庭の変化に求める意見が上がったのも当然であろう。これは不登校の原因を何らかのパーソナリティの特徴に求めるジョンソン以来のものではあるが、その特徴像は大きく変わっている。
「一般に登校拒否の児童生徒の性格は、自己決定力が弱く、協調性や融通性に乏しく、神経質である。このような性格は、本人の生得的なものもあるが、家庭における養育態度や親の性格などの要因が大きく影響する。長男長女時代に象徴される子供の数の減少や、生活の合理化によってできた時間のゆとりは、わが子の将来への期待に向けられ、過干渉、過保護と言った養育態度として現れる。また社会情勢の変化は父親像・母親像の変容にもつながり、子供の性格形成上必要な生き方を示すモデルとなりにくい場合もある。いずれにしても判断力・忍耐力・協調性に富んだ児童生徒が育ちにくい土壌が家庭内にあることは確かである。」(愛知県教育委員会『登校拒否児童生徒の指導』1989)
「いろいろ考えてしまうたちで、踏ん切りが悪く、器用に周りに合わせたり臨機応変に振る舞うのが苦手で、それでまたあれこれ考えてしまい些細なことまで気になってくるタイプで集団行動や集団の人間関係をこなすのがいかにも不得手で、学校の集団生活につまずいて登校できなくなってしまう、という子供」が増えた。この背景には少子化と豊かさが親たちに時間的・経済的ゆとりを与え過保護、過干渉な子育てとなり、学校生活をこなす社会的な力が身についていない子供達が増えた、とするものであった。
以上が、不登校の成り立ちと、その変遷の概略であるが、最後に現在の不登校の定義として二人の精神科医の見解をあげておこう。
(門信一郎)
「本人、家庭、学校、地域、社会の各々の要因(登校に関しては不利にな条件)の絡み合いによって、子供が精神的に疲労困憊し、登校することに不安を覚えるが、登校しければならないという義務感のために葛藤状態になり、ついに登校できなくなった状態」とする。
不登校は、初めは頭痛、腹痛、発熱、倦怠感という身体症状で始まることが多いが、医者には病気ではないと言われてしまうが、実際は病気ではないが元気・健康でもない「疲れた」状態と言える。
ここで言う不利な条件とは、本人の問題としては、性格(完全主義、潔癖症、感受性が強く傷つきやすいなどの登校には不利な条件になる性格)、親の側の問題としては、学校へのこだわり、学歴主義、世間体などが、学校側の問題としては、義務教育が文部省の独占企業になっていること、いじめ、などがあげられる。
(滝川一廣)
「不登校、登校拒否とは、子供が登校しない(出来ない)と言う現象と、それにまつわる葛藤状況の総称に過ぎない。発熱、腹痛と同じ症状に過ぎず、虫垂炎というような疾患単位を構成できるようなない現象ではない。」とするもの。
同じく滝川は、本文中で直接的な定義として「学校教育という営みに孕まれる何らかの要素との関連において長期欠席が生じ、そこに悩みや不安、葛藤が生まれているもの」
としている。