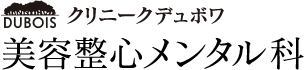マクロ精神医学?―精神科医・滝川一廣の視点
マクロ精神医学?―精神科医・滝川一廣の視点
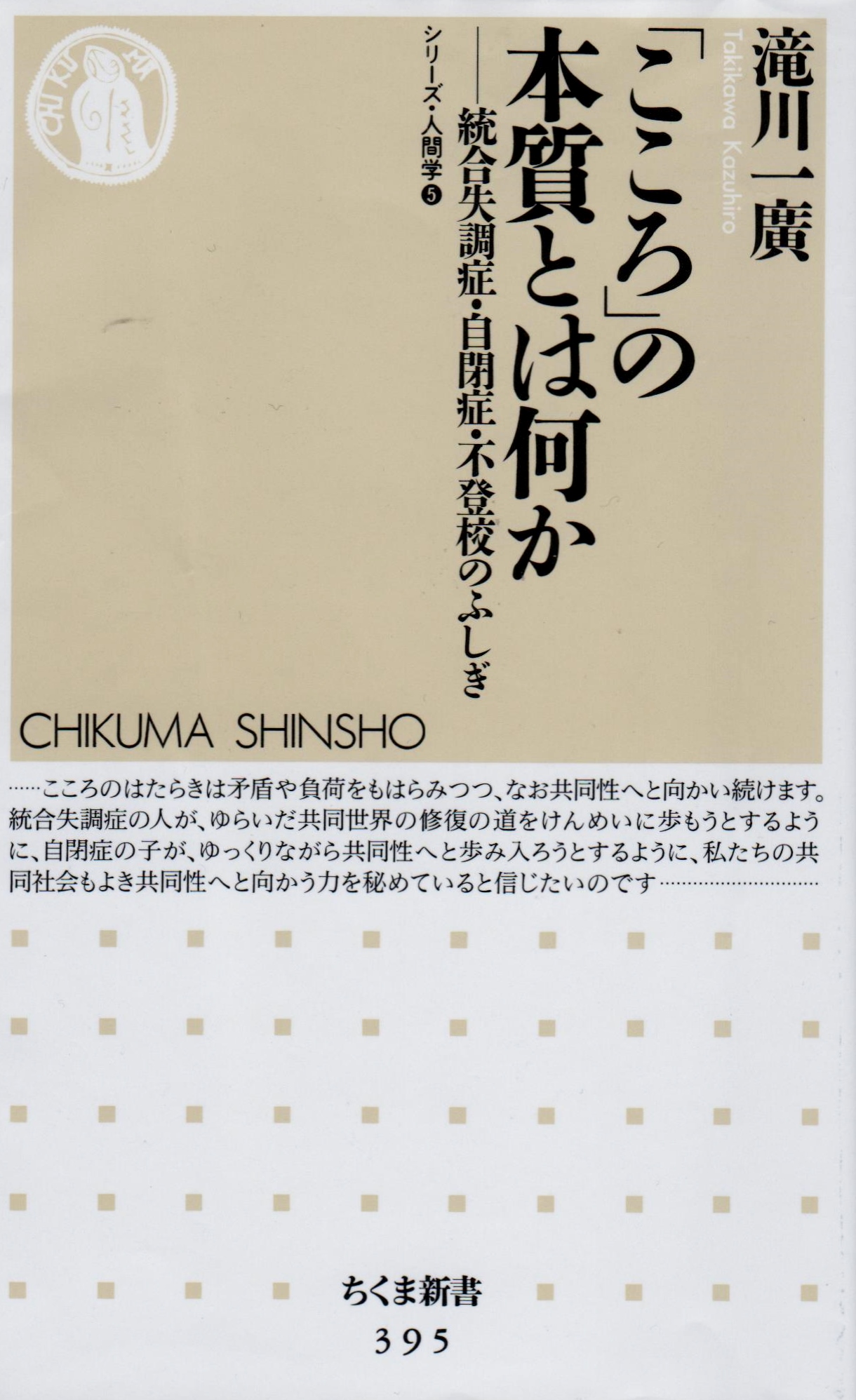
かつて、現在の我が国の精神医学が、米国の精神医学会の動向を無批判的に輸入している現状を批判し揶揄したが、それとは違う立ち位置の精神科医がいうことを知った。症状だけを操作的に扱うだけで、疾患としての成因を病理学的にみなくなった現在の精神医学の現状を嘆き、「人間学的精神病理学」を基本的な視点として、精神障害というものの症状の共通原理を探すという新しい学問的姿勢というか、精神医学が医学としての科学性を持つなら当然ともいえる姿勢を堅持しようとする精神科医のいることを知り少し安心し嬉しかった。
例えば不登校の起きる原因の意見ををめぐる混乱をリンゴが落ちる話にたとえて説明している。
<成因論についての例えーリンゴが木から落ちるのはなぜか?>
A:林檎の実、あるいは木事態に成因を求める説明法(内在因論)
実が熟して重くなった,実が腐った、ヘタが弱った、枝が枯れた
B:林檎がおかれた環境に成因を求める説明法(外在因論)
風が吹いたから、カラスがツツイタから、人が木を揺さぶったから、害虫が付いたから
C:諸要因の複合と説明する説法(複合成因論)
熟して重くなった実は落ちやすい上、熟したリンゴは食欲をそそるので、カラスがツツイタり、人間が木を揺さぶったりする可能性が高い、また熟すとヘタが弱くなり僅かな力でも枝を離れやすい。これらが複合してリンゴは落下する。
D:一概に何が成因とは言えないとする説明法(ケースバイケース論)
カラスではなく雀の場合もあろう̪、自然落下する例もあり、成因は一概にいうべきではない。林檎落下は症候群に過ぎない。
いずれも間違ってはいないが、問に対しては本質論にはなっていない。本質論は「林檎は重力があるから落ちた。」というニュートンの重力論である。
不登校の論争点は1)子供自身の何らかの問題性2)家族関係や養育の問題性3)学校教育の問題性、のいずれかに帰して説明される。
不登校成因論の定型
A.内在因論
子供ないし家庭の在り方に本質的要因を求めるもの。
サンプルA:登校拒否の児童生徒は、自己決定力が弱く、協調性や融通性に乏しく、神経質である。このような性格は生得的なものもあるが、家庭における養育態度や親の性格などの要因が大きく影響する。少子化や社会情勢の変化は親が子供のモデルになりにくい状況を作り、判断力、忍耐力、協調性に富んだ児童生徒が育ちにくい土壌があることは確かである。
すなわち、分離不安が強かったから、社会性が未熟だった、自我が弱かった、家族内に葛藤があった、学校教育が画一的になったから、受験体制や管理が強化されたから、などの各説があるが、結局「こういう場合に林檎が落ちる」「いや、こんな落ち方もある」「私の観察した林檎はこんな落ち方をした」「近頃は、こんな風な落ち方も見られる」などの諸説と同じである。仮に引力が強まれば、今まで落ちなかった林檎も落ちるようになり、その引力に相当する(引力が無ければ林檎は落ちない)マクロな本質要因、全体を貫く大局的な事象が重要であるがそれが欠如しているのである。。
B.外在因論
「学校環境」ないし、社会全体の教育環境の在り方に本質的要因を求めるもの。
サンプルB:学校教育は知育に偏り、教育内容の増量、高度化から能率一辺倒になり画一化が起こり、学校現場も多彩多様な子供一人ひとりに柔軟に対応することが困難になった。結果子供たちに大きな精神的負担がかかるようになった。さらに最近の学歴偏重、高学歴志向は受験競争を激化させ、より知育編重となりよりストレスへと追い込むものになった。
C.複合成因論
ABのブレンドしたもの
D.ケースバイケース論
問題が複雑であると言っているだけ。複雑多岐な現象から普遍的な認識を引き出す努力を放棄しているともいえる。
つまるところ、成因論はA,Bの2パターンに集約される
すなわち、分離不安が強かったから、社会性が未熟だった、自我が弱かった、家族内に葛藤があった、学校教育が画一的になったから、受験体制や管理が強化されたから、などの各説があるが、結局「こういう場合に林檎が落ちる」「いや、こんな落ち方もある」「私の観察した林檎はこんな落ち方をした」「近頃は、こんな風な落ち方も見られる」などの諸説と同じである。仮に引力が強まれば、今まで落ちなかった林檎も落ちるようになり、その引力に相当する(引力が無ければ林檎は落ちない)マクロな本質要因、全体を貫く大局的な事象が重要であるがその視点が欠如しているというのである。
滝川は、重力が根本的な共通原理であり、このようなマクロ的な視点無くして心の本質に迫れないだろうという。たしかに重力が無ければリンゴは落ちないが、しかしたとえ重力を発見しても、同じ重力下で、落ちる林檎と落ちない林檎のある理由の説明は出来ないであろうが、しかし重力の存在を無視して、落ちる理由をあれこれ言ってみたところで始まらないのも事実である。
滝川は統合失調症、双極性障害、自閉症、不登校という従来の精神病理学では病因の共通原理を見出し得なかった精神障害を、共通原理で説明して見せた。
人の存在する世界を個人的な関係世界、パーソナルな共同性世界と、個人性を離れた社会的な関係世界、インパーソナルな共同性世界の二つの位相世界に分けて考え、精神の発達を個人的(パーソナル)な共同世界から社会的(インパーソナル)な共同性世界への依存の在り方で説明し、それへの依存の関わり様で、統合失調症、双極性障害、自閉症、不登校の病理を説明してみせた。
今回は滝川のいうキーワードとなる「こころの持つ共同性」について述べる。
こころの持つ共同性(滝川一廣)
精神現象は、個体の脳の内部で生起している現象でありながら、その個体の脳の外の社会的・共同的な広がりを持った現象として初めて存在する。何を考えているかは、口にしない限りは他人には分からないが,話せば他の人にもその内容は伝わる。めいめいの脳内で生起している体験なのに、不思議なことに個体を超えて他人と共有可能になっている、この共同性が心の働きの大きな特質である。心の働きは孤立してはありえないのである。こうした心の共同的構造が認識というレベルで機能すれば、人間はそれぞれの個体の持つ生理学的な感覚知覚機能のままに世界をとらえるのではなく、絶えず「意味」や「関係」の相において世界をとらえ直して、それによって個体の認識世界を社会的に他人と共有可能なものとしていくという心の働きとなって現れる。
人間の心の働きは高度の共同性を持っており、精神発達とは、この共同性の獲得のプロセスに他ならない。
この共同性は日常レベルでは、自分以外の他人との関係に絶えず心を働かせながら精神生活を営むという形を成す。人間は、長い人類史からも複雑高度な相互依存的な生存様式を発達させてきたので、すでに心の仕組みとして他人との関係を生きざるを得ない存在となっている。私たちの心にはいつも他人がいて、精神生活とは他人との関係抜きには営まれることは不可能になっている。
人間とは他人無しでは生きられない、人間とは周りの依存性を生きる存在であるから、「依存性」を他人から基本的に保障されるかどうかは、社会的な存在に関わる重大事であり、自分は他人との関係において、安全を脅かされないか、排除されないか、承認を奪われないかと言った不安が常にあるため、「安全」「受容」「承認」があって初めて安心して生きていけるのである。
生まれたばかりの赤坊は全く無力な、全く依存的な存在であり、そこに人間の依存性の本源がある。その依存性が養育者によって十分護られて、安全が受け入れられ、存在が承認されて、養育的なかかわりを受けるところから世界との関係が始まる。これが精神発達の出発点で、依存性にこそ心の発達の最初の原点がある。
こころの形成つまり精神発達とは、認識(理解)と関係性(社会性)の両面で発達するが、関係性は、一個の個体として生まれ落ちた子供が、養育者への依存に始まって、人々が互いに依存し合う共同性の世界(個人的関係世界から社会的関係世界)に次第に歩み寄っていく過程に他ならない。
依存を本質とする我々にとって、関係における安全や受容や承認のいかんは共同性を生きることに関わる死活問題であり続ける。
人間が生きる関係世界は、大きくとらえれば二つの位相の違う世界からなっている。
一つは個人的な関係世界であり、個人性を備えたある人とある人との関係からなるパーソナルな共同性世界である。それは吉本隆明が言うところの、性(身体)に媒介された家族的な関係から生まれ、その関係を支える観念、(対幻想)の世界であり、また小浜逸郎が言うエロス的関係に当たる。エロス的関係とは、セクシャルという意味では無く、いわばその人から滲み出る風貌とか表情とか雰囲気とか息使いとか、そういう身体性をはらんだ親和性(エロス性)が関係の成り立ちに深く預かる関係という意味である。
もう一つは、そのような個人性を離れた関係の世界、社会的な関係世界、インパーソナルな共同性世界であり、すなわち社会的役割を通した関わりの世界、職場のスタッフ同士、顧客と店員など抽象性の高い関係である。これは吉本隆明の言う、共同体的な関係から生まれ、その関係を支える観念が共同体幻想であり、それは身体的媒介を持たない観念、観念的な観念であり、まさに幻想であると言えよう。小浜逸郎の言う「社会的関係」は、エロス的関係は切り捨てられ、より抽象的でインパーソナルな社会的な役割性が関係をつなぐものとなっている。さらに抽象性が高くなれば、直接の接触の無い「市民」とか「国民」と言った抽象概念によって社会的な関係のネットワークがつくられ、「国家」のような大きな相互依存の共同性を生み出し、そのような社会性の位相で我々は生きていることになる。
ところが、私達はこうした重層的で高度の共同世界を作り上げ、そこで依存し合って初めて生存を可能にしながらも、一方ではこうした共同性を不自由なもの、制約的なもの、生きにくいもいのとする違和の意識も持っている。これは、矛盾した非合理な心的作用であるが、この矛盾は私たちが共同的な存在でありつつ、一人一人が個体の存在(孤的存在)であるところからきているのではないかと思われる。
この矛盾を心の働きで見て行くと、私たちの心の働きは共同性を本質としながらも、やはり個々の頭の中で個体的に生起するものであるという矛盾にたどり着くしかない。
統合失調症のクリチカルな時期に共同的な「意味」や「関係」によって統合されている認識世界が解体に瀕するのは、しかもそのような事態が0.8%という高率(統合失調症の発病率)で生じるのは、もともと私達の心とはそうした矛盾を普遍的に抱えた存在だからではないかと思われる。
統合失調症の病態がハンチントン病のように生物学的な脳疾患として、あるいは神経症のように心理・社会的な失調としても病態が説明できないのは、個体性(一個の生物体である)と共同性(社会的な共同存在であること)との矛盾そのものを病理の根底においているからだと思われる。
この共同性と個体性との矛盾において、共同的(社会的)に生きる中で、私たちは誰しも共同世界から排される(依存を断たれる)ことへの強い恐れを持つと同時に逆に共同世界に支配され,呑み込まれる事への恐れも抱いている。
貌の見えない大きな共同性がはらむ底知れなさ、それに対する漠たる恐れと、その共同性の中で自分は真に安全なのか、という恐れがある。
近代以前の伝統社会における人々の共同意識は、地縁血縁的な共同体世界にあり、エロス的関係世界、パーソナルな共同世界とインパーソナルな共同世界はまだ溶け合って 地続きなものであったが、近代社会になって、両者がはっきり区分され、インパーソナルな巨大な共同性社会が個々人の上に覆いかぶさってきた。人々は極めて高度で抽象性の高い共同世界を生きるようになると、それとパラレルにコントラストをなすように「個人」という意識(近代自我意識)をより強く生きるようになった。
近代社会の個人と共同体とのあり方の変容を背景に近代社会以降に統合失調症が頻出するようになったとすれば、人間の心のはらむ個体性と共同性との矛盾の表れが鋭くなり失調したものが統合失調症と呼ばれる精神現象ではないか、と説明できるかもしれない。
こころの持つ共同性の大きな揺らぎが統合失調症として捉えられるなら。共同性が育つ過程の躓きが発達障害として捉えることが出来るのではないかと思われる。