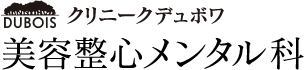「可愛くなければ、何も始まらない」身体醜形障害(症)特有の思考について
日本の精神医学が依拠するDSM5[米国精神医学会の精神疾患の診断と統計のためのマニュアル第5版]の診断基準を満たす身体醜形障害(症)と言われる人たちを日頃から診察していると、特有の決まった思考の仕方があるようだ。
それは、「まず自分が可愛いと周りから認められることが大前提である」という考え方である。何をするにも、まずそれが満たされなければ、次のステップは眼中に入って来ないのである。勉強も出来ず、学校にも行けず、外出すら出来なくなるのである。
目の前に「可愛くなければ」と言う大関門があり、それを突破しなければ、何も出来ないと主張するのだ。
「可愛くなれなければ」ということを理由に、現状から先に進むことを拒否し停止してしまうのである。
そして実はその背後に、支配的な母親や機能不全家族の存在があり、そのストレスで深く傷ついていることが少なくないのだ。
人は外見と内見(外見であらわされる以外のその人そのもの、内的人間)のトータルとして存在し、他者はそのトータルで人を評価、判断するのであり、いわば内見と外見は横並びで存在するのであるが、身体醜形障害(症)の人は判断する思考の最初にまず外見がありその先に内見ナリ社会性がある。つまり物事を縦並びでしか考え捉えることが出来ないのである。内見とは教養を積み人格を鍛えることによって得られる人間の最も大きな魅力の部分であり、それ無しでは社会と関われないのだが、それには見向きもしようとせず外見に拘り続けるのである。
これは内因性、つまり不明ではあるがどこか脳の神経学的な異常によるものではなく、神経症性、どこかに心因が存在する「考え方の問題」であり、極端になると一種の妄想に近い歪んだ確信となってしまうことさえある。
「ある物事に対して自動的に生ずる、反応に近い考え方」は元来、生来的に身についたものではなく、生まれてから今日までの個人的な体験から生じて身についたものである。従って、過去の体験を見直す作業の中で訓練をすれば、考え方は変えられ修正出来るはずである。
しかし現在の精神医学は、すべからず安易に対症療法的に投薬(身体醜形障害(症)に対してはSSRIのような抗うつ薬や抗不安薬、安定剤)し、症状の本質に眼をつむり根本的解決をしようとしないのが通常である。そればかりか、投薬することで、ある意味では社会的に病気として認知してしまい、ある種の疾病利得さえ与えてしまっているのである。病気で薬まで飲んでいるのだから仕方ない、と患者やその家族が現状の困難さから脱出する気力すら奪っているのである。
ある身体醜形障害(症)の少女が、「なぜ自分が美しい容姿にに拘るようになったのか、そしてもしそれを得ることができたら、自分の悩みは解決するだろうか」と深く洞察し著した『クラゲになりたい』という散文小説がある。
それでも、彼女は現在も積極的に前に踏み出せず苦しんでいる。
この散文はあるコンテストで受賞し、半ば公になっているし、著者の許可も得ているので、次回のこの欄に掲載の予定である。
身体醜形障害(症)に悩む人には是非読んで頂き、ご感想、ご意見を頂きたいと思っている。